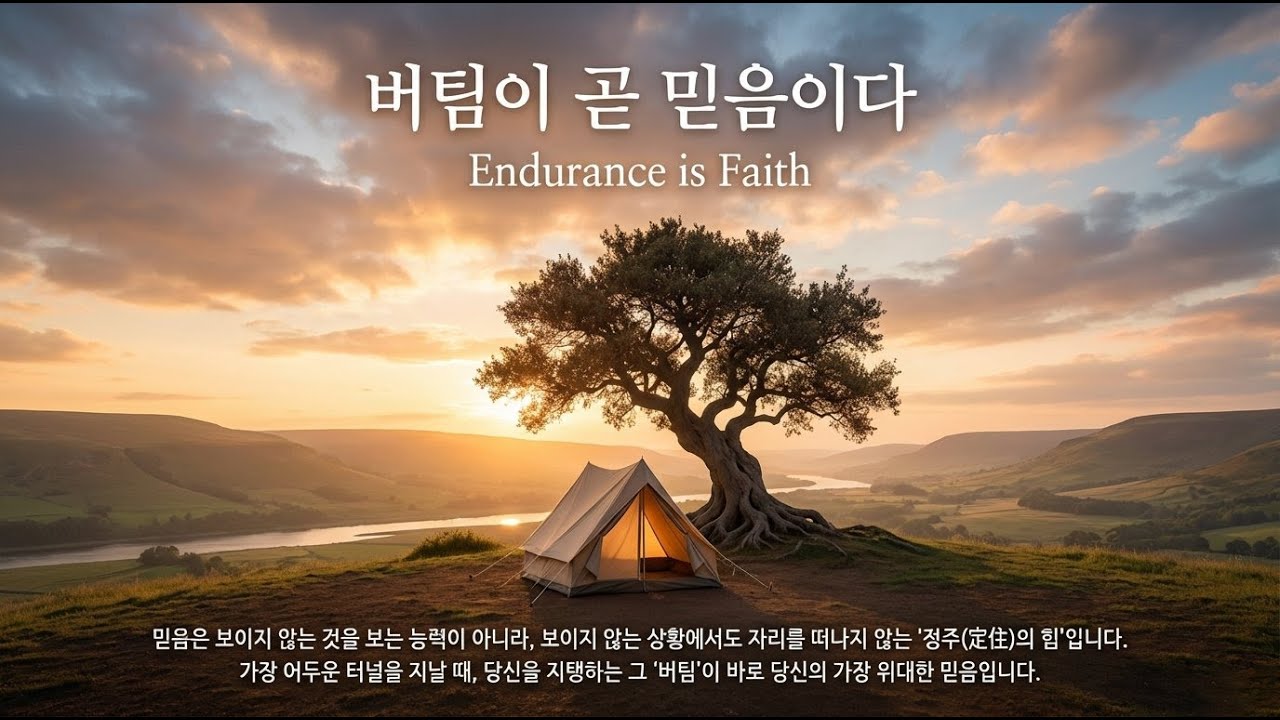т╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂ«УфгТЋЎсЃАсЃЃсѓ╗сЃ╝сѓИсѓњтюЪтЈ░сЂФсђЂсЃъсЃФсѓ│сЂ«удЈжЪ│ТЏИ14уФа32сђю42у»ђсђїсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«уЦѕсѓісђЇсѓњтЈЌжЏБу»ђ№╝ѕтЏЏТЌгу»ђ№╝ЅсЂ«ж╗ЎТЃ│сЂесЂЌсЂдтєЇУДБжЄѕсЂЌсђЂсђїсѓбсЃљсђЂуѕХсђЇсЂИсЂ«С┐Ажа╝сЂесђїуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдуЦѕсѓїсђЇсЂесЂёсЂєт╝ЪтГљжЂЊсЂ«тЈгсЂЌсђЂсЂЮсЂЌсЂдтЇЂтГЌТъХсЂ«тГцуІгсЂетљїС╝┤сѓњТи▒сЂЈуЁДсѓЅсЂЌтЄ║сЂЎсђѓ
тЈЌжЏБу»ђсЂ«уЕ║Т░ЌсЂ»сђЂсЂёсЂцсѓѓсЂЕсЂЊсЂІжЄЇсЂёсђѓсѓФсЃгсЃ│сЃђсЃ╝сЂ«СИісЂДсђїтЈЌжЏБжђ▒сђЇсЂесЂёсЂєУеђУЉЅсѓњуЏ«сЂФсЂЎсѓІуъгжќЊсђЂуДЂсЂЪсЂАсЂ«С┐АС╗░сЂ»сѓѓсЂєСИђт║дсђЂсѓѕсѓіТи▒сЂёсЂесЂЊсѓЇсЂИТІЏсЂІсѓїсѓІсђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄ№╝ѕOlivet UniversityтЅхУеГУђЁ№╝ЅуЅДтИФсЂїсђЂсЃъсЃФсѓ│сЂ«удЈжЪ│ТЏИ14уФа32сђю42у»ђсђЂсЂЎсЂфсѓЈсЂАсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«уЦѕсѓісѓњсђїсѓГсЃфсѓ╣сЃѕсЂесЂ«тљїС╝┤сђЇсЂесЂёсЂєТъаухёсЂ┐сЂДТћ╣сѓЂсЂдУфъсѓіуЏ┤сЂЮсЂєсЂесЂЌсЂЪсЂ«сѓѓсђЂсЂЮсЂ«ТІЏсЂЇсЂ«ТђДТа╝сѓњТГБуб║сЂФТј┤сѓЊсЂДсЂёсѓІсЂІсѓЅсЂасђѓсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ»сђЂсѓцсѓесѓ╣сЂ«ТюђтЙїсЂ«тцюсѓњжБЙсѓІТѓ▓тіЄуџёсЂфУѕътЈ░сЂФсЂесЂЕсЂЙсѓЅсЂфсЂёсђѓС┐АС╗░сЂїСйЋсЂФсѓѕсЂБсЂдТїЂсЂАсЂЊсЂЪсЂѕсѓІсЂ«сЂІсђЂтЙЊжаєсЂїсЂёсЂІсЂфсѓІУеђУЉЅсЂДт«їТѕљсЂЋсѓїсѓІсЂ«сЂІсђЂсЂЮсЂЌсЂдт╝ЪтГљжЂЊсЂ«т«ЪТЁІсЂїсЂЕсѓїсЂ╗сЂЕУёєсЂёсЂ«сЂІРђћРђћсЂЮсѓїсѓЅсѓњСИђТїЎсЂФжю▓сѓЈсЂФсЂЎсѓІсђЂсђїжГѓсЂ«тюДТљЙТЕЪсђЇсЂ«сѓѕсЂєсЂфта┤ТЅђсЂфсЂ«сЂДсЂѓсѓІсђѓ
УѕѕтЉ│Ти▒сЂётЄ║уЎ║уѓ╣сЂ»сЃесЃЈсЃЇсЂ«удЈжЪ│ТЏИсЂФсЂѓсѓІсђѓтЁ▒Уд│удЈжЪ│ТЏИ№╝ѕсЃъсѓ┐сѓцсЃ╗сЃъсЃФсѓ│сЃ╗сЃФсѓФ№╝ЅсЂФтЁ▒жђџсЂЌсЂдТ«ІсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«уЦѕсѓісЂїсђЂсЃесЃЈсЃЇсЂ«удЈжЪ│ТЏИсЂФсЂ»тЈЎУ┐░сЂесЂЌсЂдуЎ╗та┤сЂЌсЂфсЂёсђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂ»сђЂсЂЊсЂ«уЕ║уЎйсѓњтЇўсЂфсѓІуюЂуЋЦсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсЃесЃЈсЃЇсЂїтЇЂтГЌТъХсѓњУдІсЂцсѓЂсѓІуёдуѓ╣сЂ«жЂЋсЂёсЂесЂЌсЂдУфГсѓђсђѓт«ЪжџЏсђЂсЃесЃЈсЃЇсЂ«удЈжЪ│ТЏИсЂ»ТюђтЙїсЂ«ТЎЕжцљС╗ЦжЎЇсђЂсѓцсѓесѓ╣сЂ«жЋисЂётЉітѕЦУфгТЋЎсЂетЈќсѓісЂфсЂЌсЂ«уЦѕсѓісѓњТи▒сЂЈтЈјсѓЂ№╝ѕсЃесЃЈсЃЇ13сђю17уФа№╝ЅсђЂжђ«ТЇЋсЂ«та┤жЮбсЂИсЂеСИђТ░ЌсЂФуД╗сѓісђЂсѓцсѓесѓ╣сЂ«СИ╗т░јТеЕсЂеујІуџётеЂтј│сѓњтЅЇжЮбсЂФТі╝сЂЌтЄ║сЂЎсђѓсЂЮсЂ«ТхЂсѓїсЂ«СИГсЂДсѓцсѓесѓ╣сЂ«тєЁуџёУІдТѓХсЂїуџєуёАсЂфсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂїсђЂсЃесЃЈсЃЇсЂ»сѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«сђїСИЅт║дсЂ«Та╝жЌўсђЇсѓњуЅЕУфъсЂесЂЌсЂдтЈЇтЙЕсЂЏсЂџсђЂсѓђсЂЌсѓЇсђїС╗ісђЂсѓЈсЂЪсЂЌсЂ«т┐ЃсЂ»жењсЂёсЂДсЂёсѓІРђдРђдсђјуѕХсѓѕсђЂсЂЊсЂ«ТЎѓсЂІсѓЅсѓЈсЂЪсЂЌсѓњТЋЉсЂБсЂдсЂЈсЂасЂЋсЂёсђЈсЂеУеђсЂісЂєсЂІсђѓсЂЌсЂІсЂЌсђЂсѓЈсЂЪсЂЌсЂ»сЂЙсЂЋсЂФсЂЊсЂ«ТЎѓсЂ«сЂЪсѓЂсЂФТЮЦсЂЪсЂ«сЂасђЇсЂесЂёсЂєтЉіуЎйсѓњжђџсЂЌсЂд№╝ѕсЃесЃЈсЃЇ12:27№╝ЅсђЂтЇЂтГЌТъХсѓњтЅЇсЂФсЂЌсЂЪТЈ║сѓЅсЂјсЂеТ▒║ТќГсѓњтѕЦсЂ«С╗ЋТќ╣сЂДтюДуИ«сЂЌсЂдТЈљуц║сЂЎсѓІсђѓ
сЂасЂїт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїсђЂсЂѓсЂѕсЂдсЃъсЃФсѓ│сЂ«сѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂИуДЂсЂЪсЂАсѓњжђБсѓїсЂдУАїсЂЈуљєућ▒сЂ»ТўјуЎйсЂасђѓтЇЂтГЌТъХсЂИтљЉсЂІсЂБсЂдсђїТ▒║ТёЈсђЇсЂЌсЂЪТќ╣сЂ«ТГЕсЂ┐сЂїсђЂТёЪТЃЁсѓѓуЌЏсЂ┐сѓѓсЂфсЂёУХЁУХіуџёсЂфТЕЪТб░сЂ«сѓѕсЂєсЂФжђ▓сѓЊсЂасЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂЊсЂесђѓТёЏсЂ»Т▒║ТќГсЂасЂЉсЂДуХГТїЂсЂЋсѓїсѓІсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂТХЎсЂеТЁЪтЊГсѓњжђџжЂјсЂЌсЂдсЂфсЂіуФІсЂАуХџсЂЉсѓІсЂЊсЂеРђћРђћсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ»сЂЮсѓїсѓњТюђсѓѓС║║жќЊуџёсЂфУЅ▓тљѕсЂёсЂДУе╝УеђсЂЎсѓІсЂІсѓЅсЂДсЂѓсѓІсђѓсЂЊсЂЊсЂДуДЂсЂЪсЂАсЂїтЄ║С╝џсЂєсѓцсѓесѓ╣сЂ»сђЂсђїсЂ▓сЂЕсЂЈжЕџсЂЇсђЂТи▒сЂЈТѓ▓сЂЌсЂЙсѓїсЂЪсђЇсђѓсЂЮсЂ«УАеуЈЙсЂ»сђЂС┐АС╗░сЂїсЂЌсЂ░сЂЌсЂ░жџасЂЌсЂдсЂЌсЂЙсЂёсЂЪсЂёуюЪт«ЪсѓњТџ┤сЂЈсђѓС┐АС╗░сЂесЂ»жІ╝жЅёсЂ«уёАУАеТЃЁсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂжюЄсЂѕсѓњТі▒сЂѕсЂЪсЂЙсЂЙжђЃсЂњсЂфсЂёжЂИТіъсЂДсЂѓсѓІсђѓсЂЮсЂЌсЂдсЂЮсЂ«жЂИТіъсЂ»сђЂсђїуЦѕсѓісђЇсЂесЂёсЂєтйбсЂДсЂЌсЂІТїЂуХџсЂЌсЂфсЂёсђѓ
сђїсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсђЇсЂесЂёсЂєтљЇсЂЮсЂ«сѓѓсЂ«сЂїсђЂсЂЎсЂДсЂФУ▒АтЙ┤сЂасђѓсЃќсЃфсѓ┐сЃІсѓФсЂ»сѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«ТёЈтЉ│сѓњсђїТ▓╣ТљЙсѓіТЕЪсђЂсЂЎсЂфсѓЈсЂА oil pressesсђЇсЂеУфгТўјсЂЎсѓІсђѓсѓфсЃфсЃ╝сЃќсЂїТ▓╣сЂФсЂфсѓІсЂФсЂ»сђЂтюДсЂЌТй░сЂЋсѓїсѓІсЂЊсЂесЂїт┐ЁУдЂсЂасђѓт«ЪсЂ«сЂЙсЂЙсЂДсѓѓждЎсѓісЂ»сЂѓсѓІсЂїсђЂсЂЮсЂ«ждЎсѓісЂетЁЅсѓњжЋисЂЈт«┐сЂЎТ▓╣сЂ»сђЂтюДТљЙсЂ«ТЎѓжќЊсѓњухїсЂдућЪсЂЙсѓїсѓІсђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїсђїТљЙТ▓╣ТЅђсђЇсЂесЂёсЂєУе│УфъсЂФжЋисЂЈуЋЎсЂЙсѓІсЂ«сѓѓсђЂсЂЊсЂ«уѓ╣сѓєсЂѕсЂДсЂѓсѓІсђѓсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ»сђЂсѓцсѓесѓ╣сЂїТ▓╣Т│есЂїсѓїсЂдујІсЂесЂЌсЂдтЇ│СйЇсЂЎсѓІТГЊтЉ╝сЂ«та┤сЂесЂёсЂєсѓѕсѓісђЂујІсЂ«ТеЕтеЂсЂїтЇЂтГЌТъХсЂ«тЙЊжаєсЂФсѓѕсЂБсЂду▓ЙжїгсЂЋсѓїсѓІта┤сђЂТёЏсЂ«Т▓╣сЂїУІджЏБсЂ«тюДсЂЌТй░сЂЌсЂ«СИГсЂДТљЙсѓітЄ║сЂЋсѓїсѓІта┤сЂфсЂ«сЂасђѓ
сЂЌсЂІсѓѓсђЂсЂЮсЂ«тцюсЂ»жЂјУХісЂ«тцюсЂДсЂѓсѓІсђѓсѓцсѓесѓ╣сЂет╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂїсђЂуЦъТ«┐сЂ«сЂѓсѓІжФўсЂёсѓесЃФсѓхсЃгсЃасѓњУЃїсЂФсЂЌсђЂсѓГсЃЄсЃГсЃ│сЂ«У░исѓњТИАсЂБсЂдсѓфсЃфсЃ╝сЃќт▒▒сЂИтљЉсЂІсЂєсЂесЂЇсђЂсЂЮсЂ«УХ│тЁЃсЂФсЂ»сђЂсЂёсЂЉсЂФсЂѕсЂ«ТГ┤тЈ▓сђЂУ┤ќсЂёсЂ«У▒АтЙ┤сЂїТхЂсѓїсЂдсЂёсЂЪсЂ»сЂџсЂасђѓсЃГсЃ╝сЃъТЎѓС╗БсЂФсЃдсЃђсЃцтЈ▓сѓњУеўсЂЌсЂЪсЃесѓ╗сЃЋсѓ╣сЂ»сђЂжЂјУХісЂФуї«сЂњсѓЅсѓїсЂЪуіауЅ▓сЂ«ТЋ░сѓњжЏєУеѕсЂЌсђЂсЂѓсѓІт╣┤сЂ«жЂјУХісЂФсЂ»сђї256,500сђЇсЂ«уіауЅ▓сЂїсЂѓсЂБсЂЪсЂеУеўсЂЌсђЂСИђсЂцсЂ«сЂёсЂЉсЂФсЂѕсЂФт░ЉсЂфсЂЈсЂесѓѓтЇЂС║║сЂїтЈѓСИјсЂЌсЂЪсЂ«сЂасЂІсѓЅсђЂтцЦсЂЌсЂёуЙцУАєсЂїсѓесЃФсѓхсЃгсЃасЂИТі╝сЂЌт»ёсЂЏсЂЪсЂ«сЂасЂеС╝ЮсЂѕсѓІсђѓТЋ░сЂ«ТГБуб║сЂЋсѓњсѓЂсЂљсѓІУГ░УФќсЂїсЂѓсѓІсЂФсЂЏсѓѕсђЂсЂЮсЂ«Уеўжї▓сЂїуц║сЂЎсЂ«сЂ»т░ЉсЂфсЂЈсЂесѓѓсђЂтйЊТЎѓсЂ«сѓесЃФсѓхсЃгсЃасЂїжЂјУХісЂ«сЂЪсЂ│сЂФсђїУАђсЂеуЙцУАєсЂеуиіт╝хсђЇсЂДУєесѓїСИісЂїсѓІжЃйтИѓсЂасЂБсЂЪсЂесЂёсЂєС║Іт«ЪсЂасђѓсѓцсѓесѓ╣сЂ«тЇЂтГЌТъХсЂ»ТійУ▒АуџёсЂфТЋЎуљєсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂуЅ╣т«џсЂ«уЦГсѓісђЂуЅ╣т«џсЂ«Тћ┐Т▓╗уџёТЂљТђќсђЂуЅ╣т«џсЂ«т«ЌТЋЎуџёує▒уІѓсЂ«сЂЪсЂаСИГсЂДУхисЂЊсЂБсЂЪтЄ║ТЮЦС║ІсЂДсЂѓсѓІсЂЊсЂесѓњТђЮсЂётЄ║сЂЋсЂЏсѓІсђѓ
сЂесЂЊсѓЇсЂїт╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂ»сђЂсЂЮсЂ«тцюсѓњУ│ЏуЙјсЂ«ТГїсЂДжђџсѓіТіюсЂЉсѓІсђѓсђїтй╝сѓЅсЂ»У│ЏуЙјсЂЌсђЂсѓфсЃфсЃ╝сЃќт▒▒сЂИтЄ║сЂдУАїсЂБсЂЪсђЇсЂесЂёсЂєСИђТќЄсЂ»сђЂсЂѓсЂЙсѓісЂФуЕЈсѓёсЂІсЂДсђЂсѓђсЂЌсѓЇСИЇуЕЈсЂасђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂ»сђЂсЂЊсЂЊсЂФт╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂ«сђїТёЪУдџсЂ«ТгатдѓсђЇсѓњУдІТіюсЂЈсђѓСИ╗сЂ«тєЁсЂФсЂ»сЂЎсЂДсЂФУБЈтѕЄсѓісЂ«тЁєсЂЌсЂеТГ╗сЂ«тй▒сЂїсЂЈсЂБсЂЇсѓісЂЌсЂдсЂёсѓІсЂ«сЂФсђЂт╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂ»уЕ║Т░ЌсѓњУфГсѓЂсЂфсЂёсЂЙсЂЙУ│ЏуЙјсѓњТГїсЂёсђЂсѓёсЂїсЂдуюасѓісЂИсЂетѓЙсЂЈсђѓсЂЊсЂ«т»ЙТ»ћсЂ»сђЂт╝ЪтГљсЂЪсЂАсѓњжЮъжЏБсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«УБЁуй«сЂДсЂ»сЂфсЂёсђѓуДЂсЂЪсЂАсЂ»сЂЌсЂ░сЂЌсЂ░сђїУ│ЏуЙј№╝ЮТЋгУЎћсђЇсЂеуЪГухАсЂЎсѓІсЂїсђЂУ│ЏуЙјсЂїуЈЙт«ЪжђЃжЂ┐сЂ«ТЅІТ«хсЂФсЂфсѓісЂєсѓІсЂЊсЂесѓњТўасЂЌтЄ║сЂЎжЈАсЂДсѓѓсЂѓсѓІсђѓжЄЇсЂЋсЂФУђљсЂѕсѓЅсѓїсЂфсЂёжГѓсЂ»сђЂсЂесЂЇсЂФТГїсЂДУдєсЂёжџасЂЎсђѓсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ»сЂЮсЂ«ТГїсѓњтЅЦсЂјтЈќсѓісђЂТ«ІсЂБсЂЪућЪУ║ФсЂ«С┐АС╗░сЂ«т«ЪуЏИсѓњУдІсЂЏсѓІсђѓ
сѓцсѓесѓ╣сЂ»тЇЂСИђС║║сЂ«т╝ЪтГљсЂ«СИГсЂІсѓЅсђЂсЂЋсѓЅсЂФСИЅС║║РђћРђћсЃџсЃєсЃГсђЂсЃцсѓ│сЃќсђЂсЃесЃЈсЃЇРђћРђћсѓњжђБсѓїсЂдтЦЦсЂИтЁЦсѓЅсѓїсѓІсђѓсЂЮсѓїсЂ»уЅ╣ТеЕсЂ«сѓѕсЂєсЂФУдІсЂѕсЂдсђЂт«ЪсЂ»тљїС╝┤сЂИсЂ«УдЂУФІсЂасђѓсђїуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсЂфсЂЋсЂёсђЇсЂесЂёсЂєУеђУЉЅсЂ»сђЂтЇўсЂфсѓІУдџжєњсЂ«тЉфТќЄсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂТёЏсЂ«ТюђтЙїсЂ«тўєжАўсЂДсЂѓсѓІсђѓсЂЮсЂЌсЂдсђЂсЂЮсЂ«тўєжАўсЂїт┤ЕсѓїсѓІуъгжќЊсђЂтЇЂтГЌТъХсЂИсЂ«жЂЊсЂїсЂёсЂІсЂФтГцуІгсЂІсЂїж««ТўјсЂФсЂфсѓІсђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїу╣░сѓіУ┐ћсЂЌУфъсѓІсђїсѓГсЃфсѓ╣сЃѕсЂ«тГцуІгсђЇсЂ»сђЂсЂЙсЂЋсЂФсЂЊсЂЊсЂДТѕљуФІсЂЎсѓІсђѓСИ╗сЂ»т╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂїС╗БсѓЈсѓісЂФУЃїУ▓асЂѕсЂфсЂёжЄЇУЇисѓњуІгсѓісЂДТІЁсЂєсЂїсђЂсЂЏсѓЂсЂдтЁ▒сЂФуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсЂдсЂ╗сЂЌсЂёсЂежАўсѓЈсѓїсѓІсђѓсЂасЂїтй╝сѓЅсЂ»уюасЂБсЂдсЂЌсЂЙсЂєсђѓсђїт┐ЃсЂ»жАўсЂБсЂдсѓѓсђЂУѓЅСйЊсЂїт╝▒сЂёсђЇсЂесЂёсЂєт«БУеђсЂ»сђЂС║║жќЊтГўтюесЂ«ТДІжђасѓњСИђТќЄсЂДУДБтЅќсЂЎсѓІсђѓТёЈт┐ЌсЂ»Тќ╣тљЉсѓњуЪЦсЂБсЂдсЂёсѓІсЂ«сЂФсђЂу┐њТЁБсЂеуќ▓ті┤сЂеТЂљсѓїсЂїУ║ФСйЊсѓњТефсЂЪсЂѕсѓІсђѓсЂасЂІсѓЅС┐АС╗░сЂ»сђЂсЂёсЂцсѓѓсђїУфЊсЂёсђЇсѓѕсѓісѓѓсђїУеЊуи┤сђЇсЂФУ┐ЉсЂёсђѓсЂЮсЂЌсЂдУеЊуи┤сЂ«СИГт┐ЃсЂФсЂѓсѓІсЂ«сЂїсђЂуюасѓісЂФтІЮсЂцуЦѕсѓісЂДсЂѓсѓІсђѓ
сѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«уЦѕсѓісЂ«жаѓуѓ╣сЂ»сђЂсѓцсѓесѓ╣сЂ«тЉ╝сЂ│сЂІсЂЉсЂІсѓЅтДІсЂЙсѓІсђѓсђїсѓбсЃљсђЂуѕХсѓѕсђЇсђѓсѓбсЃљсЂ»сѓцсѓесѓ╣сЂїућесЂёсЂЪсѓбсЃЕсЃаУфъсЂДсЂѓсѓісђЂсЃЉсѓдсЃГсѓѓсЂЙсЂЪсђЂуДЂсЂЪсЂАсЂїтЙАжюісЂФсѓѕсЂБсЂдуЦъсѓњсЂЮсЂ«сѓѕсЂєсЂФтЉ╝сЂХсѓѕсЂєсЂФсЂфсЂБсЂЪсЂеУфъсѓІсђѓсЂесЂ»сЂёсЂѕсђЂсЂЮсѓїсѓњуЈЙС╗БУфъсЂДуёАТЮАС╗ХсЂФсђїсЃђсЃЄсѓБсђЇсЂ«сѓѕсЂєсЂФУ╗йсЂЈУе│сЂЎсЂЊсЂесЂФсЂ»ТЁјжЄЇсЂДсЂѓсѓІсЂ╣сЂЇсЂасЂесЂёсЂєТїЄТЉўсѓѓсЂѓсѓІсђѓсѓбсЃљсЂїтљФсѓђУдфт»єсЂЋсЂ»уб║сЂІсЂасЂїсђЂсЂЮсѓїсЂ»У╗йујЄсЂфжд┤сѓїжд┤сѓїсЂЌсЂЋсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂуЋЈсѓїсЂ«сЂєсЂАсЂ«Удфт»єсЂЋсђЂт░ітј│сЂ«сЂєсЂАсЂ«У┐ЉсЂЋсЂДсЂѓсѓІсђЂсЂеуЦътГдУђЁсЂЪсЂАсЂ»т╝иУф┐сЂЎсѓІсђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїТј┤сѓђсЂ«сѓѓсђЂсЂЮсЂ«У│фТёЪсЂасђѓтЇЂтГЌТъХсѓњтЅЇсЂФсЂЌсЂЪсѓцсѓесѓ╣сЂ»сђЂуЦъсѓњУдІуЪЦсѓЅсЂгУБЂтѕцт«ўсЂесЂЌсЂдсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсђїсѓЈсЂЪсЂЌсЂ«уѕХсђЇсЂетЉ╝сЂ░сѓїсѓІсђѓсЂЮсЂ«СИђУфъсЂїсђЂС┐АС╗░сЂ«ТюђтЙїсЂ«Тћ»ТЪ▒сЂесЂфсѓІсђѓуѕХсЂ«ТёЏсЂИсЂ«уб║С┐АсЂїт┤ЕсѓїсЂЪуъгжќЊсђЂтЙЊжаєсЂ»сЂЪсЂАсЂЙсЂАухХТюЏсЂИтцЅУ│фсЂЎсѓІсЂІсѓЅсЂасђѓ
сЂЌсЂІсЂЌсђЂсЂЮсЂ«уб║С┐АсЂїТёЪТЃЁсѓњТХѕсЂЌсЂдсЂЈсѓїсѓІсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂфсЂёсђѓсѓцсѓесѓ╣сЂ»сђїсЂЊсЂ«ТЮ»сѓњсѓЈсЂЪсЂЌсЂІсѓЅтЈќсѓітј╗сЂБсЂдсЂЈсЂасЂЋсЂёсђЇсЂеТ▒ѓсѓЂсѓІсђѓсЂЊсѓїсЂ»тЏъжЂ┐сЂ«уйфсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂС║║жќЊТђДсЂ«ТГБуЏ┤сЂЋсЂДсЂѓсѓІсђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїсЂЊсЂ«у«ЄТЅђсѓњсђїТЁ░сѓЂсђЇсЂеУфГсѓђсЂ«сЂ»сђЂС┐АС╗░УђЁсЂїТі▒сЂЈТЂљсѓїсѓёжюЄсЂѕсЂїсђЂсЂЮсЂ«сЂЙсЂЙСИЇС┐АсЂ«Уе╝ТІасЂДсЂ»сЂфсЂёсЂЊсЂесѓњуц║сЂЎсЂІсѓЅсЂасђѓтЋЈжАїсЂ»ТЂљсѓїсЂїсЂѓсѓІсЂІсЂфсЂёсЂІсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсЂЮсЂ«ТЂљсѓїсѓњУф░сЂ«тЅЇсЂИТїЂсЂБсЂдУАїсЂЈсЂІсЂДсЂѓсѓІсђѓсѓцсѓесѓ╣сЂ»ТЂљсѓїсѓњС║║сђЁсЂФУфЄт╝хсЂЌсЂдУе┤сЂѕсѓІсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂуѕХсЂФућ│сЂЌСИісЂњсѓІсђѓсЂЮсЂЌсЂдсЂЎсЂљсЂФуЦѕсѓісЂ«тљЉсЂЇсѓњтцЅсЂѕсѓІсђѓсђїсЂЌсЂІсЂЌсђЂсѓЈсЂЪсЂЌсЂ«ТюЏсЂ┐сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсЂѓсЂфсЂЪсЂ«тЙАт┐ЃсЂ«сЂЙсЂЙсЂФсђѓсђЇсЂЊсѓїсЂ»УФдсѓЂсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂС┐Ажа╝сЂФтЪ║сЂЦсЂЈУЄфти▒тДћсЂГсЂДсЂѓсѓІсђѓсѓГсЃфсѓ╣сЃѕТЋЎсЂ«тЙЊжаєсЂесЂ»ТёЪТЃЁсЂ«СИЇтюесЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂТёЪТЃЁсѓњУХЁсЂѕсЂджќбС┐ѓсѓњжЂИсЂ│тЈќсѓІсЂЊсЂесЂасђѓ
сЂЊсЂ«тЙЊжаєсѓњуљєУДБсЂЎсѓІсЂФсЂ»сђЂТЌДу┤ёсЂ«жаљУеђуџёУЃїТЎ»сѓѓТЃ│УхисЂЌсЂЪсЂёсђѓсѓцсѓесѓ╣сЂ»т╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂФсђїуЅДУђЁсѓњТЅЊсЂдсђЂсЂЮсЂєсЂЎсѓїсЂ░уЙісЂ»ТЋБсѓЅсЂЋсѓїсѓІсђЇсЂесЂёсЂєУеђУЉЅсѓњт╝ЋсЂЇ№╝ѕсЃъсЃФсѓ│14уФа№╝ЅсђЂсѓ╝сѓФсЃфсЃц13уФа7у»ђсЂ«жаљУеђсѓњУЄфсѓЅсЂ«ТГЕсЂ┐сЂФжЄЇсЂГсѓІсђѓсђїуЅДУђЁсѓњТЅЊсЂдсђЂсЂЎсѓІсЂеуЙісЂ»ТЋБсѓІсђѓсђЇтЇЂтГЌТъХсЂ»тЂХуЎ║С║ІТЋЁсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсђїуЪЦсѓісЂцсЂцсђЇтЁЦсЂБсЂдУАїсЂІсѓїсЂЪжЂЊсЂДсЂѓсѓІсђѓсЂЮсѓїсЂДсѓѓсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂДсѓцсѓесѓ╣сЂ»сђЂсЂЮсЂ«жЂЊсѓњуЦѕсѓісЂФсѓѕсЂБсЂдсѓѓсЂєСИђт║дтЈЌсЂЉтЈќсѓіуЏ┤сЂЎсђѓС║ѕт«џсЂетЙЊжаєсЂ»сЂЊсЂЊсЂДтЏ║сЂЈухљсЂ│тљѕсѓЈсЂЋсѓїсѓІсђѓуѕХсЂ«тЙАт┐ЃсЂїтќёсЂёсЂеуЪЦсЂБсЂдсЂёсЂдсѓѓсђЂсЂЮсЂ«жЂЊсЂ«УІдсЂЋсЂїТХѕсЂѕсѓІсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂфсЂёсђѓсЂасЂїсђЂсЂЮсЂ«УІдсЂЋсЂїТёЈтЉ│сѓњТїЂсЂАтДІсѓЂсѓІсђѓсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«тЙЊжаєсЂ»сђїС╗ЋТќ╣сЂїсЂфсЂёсђЇсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсђїсЂѓсЂфсЂЪсЂїтќёсЂёсЂіТќ╣сЂасЂІсѓЅсђЂС┐АсЂўсЂджђ▓сѓђсђЇсЂДсЂѓсѓІсђѓ
т╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂ«УДБжЄѕсЂ«сѓѓсЂєСИђсЂцсЂ«т╝исЂ┐сЂ»сђЂсЂЊсЂ«ТюгТќЄсѓњсђїуЦътГдуџёТГБУДБсђЇсЂесЂЌсЂдсЂасЂЉТЅ▒сѓЈсЂџсђЂсђїС║║жќЊсЂ«уЈЙт«ЪсђЇсЂИт╝ЋсЂЇСИІсѓЇсЂЎуѓ╣сЂФсЂѓсѓІсђѓуДЂсЂЪсЂАсЂ»сЂЌсЂ░сЂЌсЂ░сѓцсѓесѓ╣сЂ«тЙЊжаєсѓњУфъсѓісЂфсЂїсѓЅсђЂсЂЮсЂ«тЙЊжаєсЂїсЂЕсѓїсЂ╗сЂЕсЂ«т┐ЃуљєуџёжЄЇУЇисѓњС╝┤сЂєсЂ«сЂІсђЂсЂЮсЂ«жЄЇУЇисЂїУ║ФСйЊсЂ«тЈЇт┐юРђћРђћТ▒ЌсђЂтЉ╝тљИсђЂж╝ЊтІЋсђЂжюЄсЂѕРђћРђћсЂесЂЌсЂдсЂёсЂІсЂФтЎ┤сЂЇтЄ║сЂЌсЂЪсЂ«сЂІсЂЙсЂДТЃ│тЃЈсЂЌсЂЪсЂїсѓЅсЂфсЂёсђѓсЂасЂїудЈжЪ│ТЏИсЂїсѓЈсЂќсѓЈсЂќсђїжЕџсЂЇсђЇсЂесђїТѓ▓сЂЌсЂ┐сђЇсѓњУеўсЂЌсЂЪС║Іт«ЪсЂ»сђЂуЦъсЂїС║║жќЊсЂ«т╝▒сЂЋсѓњС┐АС╗░сЂ«тцќсЂИУ┐йТћЙсЂЌсЂфсЂІсЂБсЂЪсЂЊсЂесѓњТёЈтЉ│сЂЎсѓІсђѓТЋЎС╝џсЂїсђїт╝исЂЈУдІсЂѕсѓІС┐АС╗░сђЇсЂ░сЂІсѓісѓњжЎ│тѕЌсЂЎсѓІсЂесђЂтѓисЂцсЂёсЂЪС║║сЂ»УЄфтѕєсЂ«ТёЪТЃЁсѓњуйфТѓфТёЪсЂФтцЅсЂѕсЂджБ▓сЂ┐УЙ╝сѓЊсЂДсЂЌсЂЙсЂєсђѓсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ»сЂЮсЂ«ТГфсЂ┐сѓњТГБсЂЎсђѓсђїТЂљсѓїсЂїсЂѓсѓІсђЇсЂесЂёсЂєтЉіуЎйсЂ»сђЂсЂЎсЂДсЂФС┐АС╗░сЂ«тц▒ТЋЌсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂС┐АС╗░сЂїуЦѕсѓісЂесЂёсЂєтйбсЂДУЄфсѓЅсѓњТГБуЏ┤сЂФУАесЂЎТюђтѕЮсЂ«СИђТГЕсЂФсЂфсѓісЂєсѓІсђѓ
сЂЊсЂЊсЂДсђїТЮ»сђЇсЂесЂёсЂєсѓцсЃАсЃ╝сѓИсЂ»сђЂсЂЋсѓЅсЂФУ▒ісЂІсЂФсЂфсѓІсђѓУЂќТЏИсЂФсЂісЂёсЂдТЮ»сЂ»сђЂсЂесЂЇсЂФУБЂсЂЇсЂеТђњсѓісѓњТїЄсЂЌсђЂсЂесЂЇсЂФУІджЏБсЂ«тѕєсЂЉтЅЇсѓњТёЈтЉ│сЂЎсѓІсђѓсѓцсѓесѓ╣сЂїсђїсЂЊсЂ«ТЮ»сђЇсѓњУфъсѓІсЂесЂЇсђЂсЂЮсѓїсЂ»УѓЅСйЊуџёУІдуЌЏсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈсђЂуйфС║║сЂ«ТЅІсЂФТИАсЂЋсѓїсѓІт▒ѕУЙ▒сђЂуљєСИЇт░йсђЂжќбС┐ѓсЂ«УБЈтѕЄсѓісђЂсЂЮсЂЌсЂдуЦъсЂІсѓЅТќГсЂАтѕЄсѓЅсѓїсЂЪсѓѕсЂєсЂФТёЪсЂўсѓЅсѓїсѓІсђїУдІТЇесЂдсѓЅсѓїсђЇсЂ«Ти▒ТихсЂЙсЂДтљФсѓЊсЂДсЂёсѓІсђѓсѓєсЂѕсЂФсѓцсѓесѓ╣сЂ«уЦѕсѓісЂ»сђЂуЅЕуљєуџёуЌЏсЂ┐сѓњжЂ┐сЂЉсЂЪсЂёТюгУЃйсѓњУХЁсЂѕсђЂтГўтюесЂЮсЂ«сѓѓсЂ«сЂїт┤ЕсѓїУљйсЂАсЂЮсЂєсЂфТќГт┤ќсЂДсЂ«тЈФсЂ│сЂДсЂѓсѓІсђѓсЂасЂїсЂЮсЂ«тЈФсЂ│сЂїсђЂсђїсѓбсЃљсђЇсЂесЂёсЂєтЉ╝сЂ│сЂІсЂЉсѓњТЅІТћЙсЂЋсЂфсЂёсЂЊсЂесЂїТ▒║т«џуџёсЂасђѓТёЪТЃЁсЂ»ТИдти╗сЂЈсЂ«сЂФсђЂжќбС┐ѓсЂ»тѕЄсѓїсЂфсЂёсђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїт╝иУф┐сЂЎсѓІсѓѕсЂєсЂФсђЂС┐АС╗░сЂ«тЇ▒ТЕЪсЂ»ухљт▒ђсђЂсђїуѕХсЂ«ТёЏсЂИсЂ«уб║С┐АсђЇсЂїТЈ║сѓЅсЂљсЂесЂЇсЂФУефсѓїсѓІсђѓТёЏсѓњуќЉсЂБсЂЪуъгжќЊсђЂтЙЊжаєсЂ»уЙЕтІЎсЂесЂфсѓісђЂуЙЕтІЎсЂ»уќ▓т╝ісЂИсЂцсЂфсЂїсѓІсђѓжђєсЂФТёЏсѓњС┐АсЂўсЂЪуъгжќЊсђЂтЙЊжаєсЂ»УІдуЌЏсЂ«СИГсЂДсѓѓТёЈтЉ│сѓњТїЂсЂцжЂИТіъсЂесЂфсѓІсђѓ
т╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂ«уюасѓісЂ»сђЂсЂЮсЂ«жЂИТіъсЂ«тЈЇт»ЙтЂ┤сѓњуц║сЂЎсђѓсЃџсЃєсЃГсЂ»уЏ┤тЅЇсЂФсђїсЂѓсЂфсЂЪсЂеСИђуињсЂФТГ╗сѓЊсЂДсѓѓсђЂТ▒║сЂЌсЂдсЂѓсЂфсЂЪсѓњуЪЦсѓЅсЂфсЂёсЂфсЂЕсЂесЂ»УеђсЂёсЂЙсЂЏсѓЊсђЇсЂеУеђсЂБсЂЪсђѓсЂесЂЊсѓЇсЂїжќЊсѓѓсЂфсЂЈсђЂтй╝сЂ»СИђТЎѓжќЊсЂЪсѓісЂесѓѓуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсѓЅсѓїсЂфсЂёсђѓсЂЊсЂ«уД╗сѓЇсЂёсЂ»сђЂсЃџсЃєсЃГсЂасЂЉсЂ«тЋЈжАїсЂДсЂ»сЂфсЂёсђѓС║║сЂ»сЂЪсЂёсЂдсЂёсђЂТ▒║ТёЈсЂЎсѓІсЂесЂЇсЂФсЂ»УЄфтѕєсѓњжЂјтцДУЕЋСЙАсЂЌсђЂУђљсЂѕсѓІсЂесЂЇсЂФсЂ»УЄфтѕєсѓњжЂјт░ЈУЕЋСЙАсЂЎсѓІсђѓТ▒║ТёЈсЂ«УеђУЉЅсЂ»тцДсЂЇсЂёсЂїсђЂУђљсЂѕсѓІТіђУАЊсЂ»У▓ДсЂЌсЂёсђѓсЂасЂІсѓЅсѓцсѓесѓ╣сЂ»т╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂФсђїУфўТЃЉсЂФжЎЦсѓЅсЂфсЂёсѓѕсЂєсђЂуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдуЦѕсѓісЂфсЂЋсЂёсђЇсЂеУеђсѓЈсѓїсѓІсђѓУфўТЃЉсЂесЂ»тђФуљєуџёсЂфуйфсЂИсЂ«УфўсЂёсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈсђЂжќбС┐ѓсѓњТіЋсЂњтЄ║сЂЋсЂЏсѓІуќ▓ті┤сђЂУ▓гС╗╗сѓњтЏъжЂ┐сЂЋсЂЏсѓІТЂљсѓїсђЂС┐АС╗░сѓњсђїсЂѓсЂесЂДсђЇсЂФтЁѕт╗ХсЂ░сЂЌсЂЋсЂЏсѓІуёАТёЪУдџсЂЙсЂДтљФсѓђсђѓуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесЂ»сђЂу▓ЙуЦъУФќсЂ«тІЮтѕЕсЂДсѓѓТёЪТЃЁсЂ«жФўТЈџсЂДсѓѓсЂфсЂЈсђЂжѕЇсЂБсЂдсЂёсЂЈт┐ЃсѓњуЦъсЂ«сЂ╗сЂєсЂИтєЇсЂ│тљЉсЂЉуЏ┤сЂЎт░ЈсЂЋсЂфтЈЇтЙЕсЂДсЂѓсѓІсђѓ
т╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂ»сђЂсЂЊсЂ«ТюгТќЄсѓњжђџсЂЌсЂдсђїсѓГсЃфсѓ╣сЃѕсЂесЂ«тљїС╝┤сђЇсЂесЂ»ухљт▒ђсђЂсђїтЁ▒сЂФуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесђЇсЂасЂетќџУхисЂЎсѓІсђѓтљїС╝┤сЂесЂ»тљїсЂўуЕ║жќЊсЂФсЂёсѓІсЂЊсЂесЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂтљїсЂўжќбт┐ЃсЂетљїсЂўжЄЇсЂЋсѓњтѕєсЂІсЂАтљѕсЂєсЂЊсЂесЂасђѓсЂЮсЂ«тцюсђЂт╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂ»сѓцсѓесѓ╣сЂетљїсЂўтюњсЂФсЂёсЂЪсЂїсђЂтљїсЂўтцюсѓњућЪсЂЇсЂфсЂІсЂБсЂЪсђѓсѓцсѓесѓ╣сЂ«тцюсЂ»уЦѕсѓісЂ«тцюсЂДсЂѓсѓісђЂт╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂ«тцюсЂ»уЮАуюасЂ«тцюсЂасЂБсЂЪсђѓсЂЮсЂЌсЂдсЂЮсЂ«жџћсЂЪсѓісЂїсђЂсѓцсѓесѓ╣сѓњсЂёсЂБсЂЮсЂєтГцуІгсЂФсЂЎсѓІсђѓуДЂсЂЪсЂАсѓѓС╝╝сЂдсЂёсѓІсђѓуц╝ТІЮсЂ«тИГсЂФсЂёсЂдсѓѓсђЂУф░сЂІсЂ«уЌЏсЂ┐сЂ«тЅЇсЂФсЂёсЂдсѓѓсђЂуДЂсЂЪсЂАсЂ»сЂЌсЂ░сЂЌсЂ░сђїуюасЂБсЂЪт┐ЃсђЇсЂДтГўтюесЂЎсѓІсђѓжќбт┐ЃсЂ»тѕЦсЂ«сЂесЂЊсѓЇсЂФсЂѓсѓісђЂТёЏсЂ»уќ▓сѓїсЂдсЂісѓісђЂУ▓гС╗╗сЂ»жЄЇсЂёсђѓсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ»сђЂсЂЮсЂ«уюасЂБсЂЪт┐ЃсѓњТЈ║сЂЋсЂХсЂБсЂдУхисЂЊсЂЎсђѓсђїсЂѓсЂфсЂЪсЂїсЂЪсЂ»сЂЊсЂЊсЂФсЂёсЂдсђЂуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсЂфсЂЋсЂёсђЇсЂесЂёсЂєУеђУЉЅсЂ»сђЂУІдсЂЌсЂ┐сЂ«тцюсЂФсѓѓтЁ▒тљїСйЊсѓњУдІТЇесЂдсЂфсЂІсЂБсЂЪсѓГсЃфсѓ╣сЃѕсЂ«сЂЌсѓІсЂЌсЂДсѓѓсЂѓсѓІсђѓТюђтЙїсЂ«уъгжќЊсЂЙсЂДсђїтЁ▒сЂФсђЇсѓњТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсЂЪсЂІсѓЅсЂасђѓ
сЂЌсЂІсЂЌудЈжЪ│ТЏИсЂ«тєитЙ╣сЂфТГБуЏ┤сЂЋсЂ»сђЂсЂЮсЂ«Т▒ѓсѓЂсЂїжђђсЂЉсѓЅсѓїсЂЪсЂЊсЂесѓњжџасЂЋсЂфсЂёсђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїсђїтГцуІгсђЇсѓњУфъсѓІсЂесЂЇсђЂсЂЮсѓїсЂ»ТёЪтѓиуџёС┐«УЙъсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂТЋЉТИѕтЈ▓уџёС║Іт«ЪсЂДсЂѓсѓІсђѓУф░сѓѓС╗БсѓЈсѓісЂФсЂфсѓїсЂфсЂётЙЊжаєсѓњсѓцсѓесѓ╣сЂїуІгсѓісЂДТІЁсЂёсђЂТюђсѓѓУ┐ЉсЂёт╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂДсЂЋсЂѕсЂЮсЂ«жЄЇсЂЋсЂФтљїС╝┤сЂДсЂЇсЂфсЂІсЂБсЂЪсђѓсЂЊсЂЊсЂДуДЂсЂЪсЂАсЂ»тЇЂтГЌТъХсЂ«ТЂхсЂ┐сѓњсЂЋсѓЅсЂФТўјуъГсЂФУфГсѓђсђѓтЇЂтГЌТъХсЂ»сђЂуДЂсЂЪсЂАсЂїтЁ▒сЂФТїЂсЂАСИісЂњсЂЪТЦГуИЙсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂуДЂсЂЪсЂАсЂїуюасЂБсЂдсЂёсѓІжќЊсЂФуІгсѓісЂДТїЂсЂАСИісЂњсѓЅсѓїсЂЪТЋЉсЂёсЂДсЂѓсѓІсђѓсЂасЂІсѓЅТЂхсЂ┐сЂ»т«ЅсЂБсЂйсЂЈсЂфсѓЅсЂфсЂёсђѓсѓђсЂЌсѓЇТЂхсЂ┐сЂ»сђЂсђїУЄфтѕєсЂїтЈѓСИјсЂДсЂЇсЂфсЂІсЂБсЂЪТёЏсђЇсѓєсЂѕсЂФсђЂсЂёсЂБсЂЮсЂєуЌЏсЂёсђѓсЂЮсЂ«уЌЏсЂ┐сЂїсђЂуДЂсЂЪсЂАсѓњтєЇсЂ│уЏ«УдџсѓЂсЂЋсЂЏсѓІтІЋтіЏсЂесЂфсѓІсђѓ
т╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїсЃъсЃФсѓ│сЂ«сђїУІЦУђЁсђЇсЂ«УЕ▒сѓњС╗ўсЂЉтіасЂѕсѓІсЂ«сѓѓсђЂсЂЙсЂЋсЂФсЂЊсЂ«сђїтЈѓСИјсЂДсЂЇсЂфсЂЋсђЇсЂ«ТЂЦсѓњТГБжЮбсЂІсѓЅУдІсЂцсѓЂсЂЋсЂЏсѓІсЂЪсѓЂсЂасђѓС║║сЂ»ТЎ«жђџсђЂУЄфтѕєсЂ«УІ▒жЏёУГџсѓњУеўжї▓сЂЌсЂЪсЂїсѓІсђѓсЂесЂЊсѓЇсЂїсЃъсЃФсѓ│сЂ«удЈжЪ│ТЏИсЂФсЂ»сђЂТёЈтцќсЂФсѓѓУІ▒жЏёсЂїсЂёсЂфсЂёсђѓжђЃсЂњсѓІт╝ЪтГљсЂЪсЂАсђЂуюасѓІтЈІсђЂТ▓ѕж╗ЎсЂЎсѓІуЙцУАєсђЂсЂЮсЂЌсЂдуІгсѓіуЦѕсѓІсѓцсѓесѓ╣сЂїсЂёсѓІсЂасЂЉсЂасђѓсЂЊсЂ«тЈЎУ┐░сЂ«Тќ╣тљЉТђДсЂїсђЂудЈжЪ│сѓњТюгуЅЕсЂФсЂЎсѓІсђѓудЈжЪ│сЂесЂ»С║║жќЊсЂ«жЂћТѕљсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂуЦъсЂ«С╗ІтЁЦсЂасЂІсѓЅсЂДсЂѓсѓІсђѓуДЂсЂЪсЂАсЂїтќёсЂЈсЂфсЂБсЂЪсЂІсѓЅТЋЉсЂёсЂїТЮЦсЂЪсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсђѓуДЂсЂЪсЂАсЂїуёАтіЏсЂфуъгжќЊсЂФсѓѓсђЂТёЏсЂїУФдсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂІсЂБсЂЪсЂІсѓЅТЋЉсЂёсЂїТЮЦсЂЪсЂ«сЂасђѓ
сЂасЂІсѓЅсЂесЂёсЂБсЂдсђЂсЂЊсЂ«уЅЕУфъсЂїсђїсЂЕсЂєсЂЏуДЂсЂЪсЂАсЂ»сЂДсЂЇсЂфсЂёсЂ«сЂасЂІсѓЅжЂЕтйЊсЂФућЪсЂЇсѓѕсЂєсђЇсЂесЂёсЂєтЁЇуйфугдсѓњСИјсЂѕсѓІсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂфсЂёсђѓсѓђсЂЌсѓЇжђєсЂДсЂѓсѓІсђѓсѓцсѓесѓ╣сЂ«тГцуІгсѓњуЪЦсЂБсЂЪУђЁсЂ»сђЂсѓѓсЂ»сѓёСИ╗сѓњуІгсѓісЂФсЂЌсЂдсЂісЂЇсЂЪсЂЈсЂфсЂёсђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїТюђтЙїсЂФсђїС╗іт║дсЂ»уДЂсЂЪсЂАсЂїтљїС╝┤сЂЌсЂфсЂЉсѓїсЂ░сЂфсѓЅсЂфсЂёсђЇсЂеС┐ЃсЂЎсЂ«сЂ»сђЂсЂЊсЂ«сѓєсЂѕсЂасђѓС┐АС╗░сЂ»сЂёсЂцсѓѓжЂЁсЂёсђѓуДЂсЂЪсЂАсЂ»С║ІсЂїжЂјсЂјсЂдсЂІсѓЅсђЂсѓѕсЂєсѓёсЂЈТёЈтЉ│сЂФТ░ЌсЂЦсЂЈсЂЊсЂесЂїтцџсЂёсђѓт╝ЪтГљсЂЪсЂАсѓѓтЙЕТ┤╗сЂ«тЙїсЂФсЂфсЂБсЂдтѕЮсѓЂсЂдсђЂсѓцсѓесѓ╣сЂїУф░сЂДсЂѓсЂБсЂЪсЂІсђЂсЂЮсЂ«тцюсЂїСйЋсЂДсЂѓсЂБсЂЪсЂІсѓњсђЂсѓѕсѓіж««ТўјсЂФТѓЪсЂБсЂЪсђѓсЂЌсЂІсЂЌтЈЌжЏБу»ђсЂ»сђЂсђїтЙїТѓћсЂ«ТЎѓжќЊсђЇсѓњсђїС║ѕжў▓сЂ«ТЎѓжќЊсђЇсЂИтцЅсЂѕсѓѕсЂеТ▒ѓсѓЂсѓІсђѓжЂЁсѓїсЂдТхЂсЂЎТХЎсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈсђЂсЂёсЂЙуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесЂФсѓѕсЂБсЂдсђЂСИ╗сЂ«жЂЊсЂФт┐юуГћсЂЏсѓѕсЂесЂёсЂєсЂ«сЂДсЂѓсѓІсђѓ
сЂЊсЂ«т┐юуГћсЂ»сђЂТЌЦтИИсЂ«УеђУЉЅсЂИу┐╗Уе│сЂЋсѓїсЂГсЂ░сЂфсѓЅсЂфсЂёсђѓсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«уЦѕсѓісЂ»сђЂУЂќсЂфсѓІта┤ТЅђсЂ«ТёЪтІЋсЂесЂЌсЂдсЂасЂЉТ«ІсѓІсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсђѓсђїуДЂсЂ«ТюЏсЂ┐сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЇсЂесЂёсЂєСИђТќЄсЂ»сђЂС╝џУГ░т«цсЂДсЂ«жЂИТіъсђЂт«Хт║ГсЂДсЂ«УЉЏУЌцсђЂсЂіжЄЉсЂеТЎѓжќЊсЂ«ућесЂёТќ╣сђЂжќбС┐ѓсЂ«Уфат«ЪсђЂУхдсЂЌсЂ«Т▒║ТќГсЂ«СИГсЂДтЁиСйЊтїќсЂЋсѓїсѓІсђѓУЄфтѕєсЂ«ТюЏсЂ┐сѓњжЎЇсѓЇсЂЎсЂесЂ»сђЂУЄфтѕєсЂ«тГўтюесѓњТХѕсЂЎсЂЊсЂесЂДсЂ»сЂфсЂёсђѓсѓѕсѓітцДсЂЇсЂфТёЏсЂ«уДЕт║ЈсЂ«СИГсЂИУЄфтѕєсѓњжЁЇуй«сЂЎсѓІсЂЊсЂесЂасђѓсЂЮсѓїсЂ»жЮътИИсЂФУЃйтІЋуџёсЂфтќХсЂ┐сЂДсЂѓсѓІсђѓсЂѓсѓІТЌЦсЂФсЂ»сђїТГБсЂЌсЂёжЂИТіъсђЇсЂїсђїТљЇсђЇсЂФУдІсЂѕсѓІсЂІсѓѓсЂЌсѓїсЂфсЂёсЂЌсђЂТ▓ѕж╗ЎсЂїсђїТЋЌтїЌсђЇсЂФУдІсЂѕсѓІсЂІсѓѓсЂЌсѓїсЂфсЂёсЂЌсђЂУхдсЂЌсЂїсђїт╝▒сЂЋсђЇсЂеУфцУДБсЂЋсѓїсѓІсЂІсѓѓсЂЌсѓїсЂфсЂёсђѓсЂасЂїсѓГсЃфсѓ╣сЃѕсЂ»сђЂт╝▒сЂЋсЂ«СИГсЂФт╝исЂЋсЂїуЈЙсѓїсѓІжЂЊсѓњТГЕсЂЙсѓїсЂЪсђѓсЃЉсѓдсЃГсЂїсђїсѓЈсЂЪсЂЌсЂїт╝▒сЂёсЂесЂЇсЂФсЂЊсЂЮт╝исЂёсђЇсЂетЉіуЎйсЂДсЂЇсЂЪсЂ«сѓѓсђЂсЂЮсЂ«жЂЊсЂ«УФќуљєсѓњтГдсѓЊсЂасЂІсѓЅсЂДсЂѓсѓІсђѓ
т╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂ«УфгТЋЎсЂФсЂ»сђЂсЂЊсЂ«жђєУфгсѓњТј┤сѓђуЅДС╝џуџёТёЪУдџсЂїсЂѓсѓІсђѓтй╝сЂ»С┐АС╗░сѓњсђїтІЮтѕЕсЂ«тїЁУБЁу┤ЎсђЇсЂФсЂЌсЂфсЂёсђѓсѓђсЂЌсѓЇуДЂсЂЪсЂАсЂ«у▓ЌсЂЋсѓњУфЇсѓЂсЂЋсЂЏсђЂсЂЮсЂ«у▓ЌсЂЋсѓєсЂѕсЂФсЂЋсѓЅсЂФТи▒сЂЈуЦѕсѓІсѓѕсЂєт░јсЂЈсђѓсђїт┐ЃсЂ»жАўсЂБсЂдсѓѓсђЂУѓЅСйЊсЂїт╝▒сЂёсђЇсЂесЂёсЂєУеђУЉЅсЂ»ТЋЌтїЌт«БУеђсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂуЦѕсѓісЂ«ТѕдуЋЦсЂасђѓжГѓсЂїТюгтйЊсЂФжАўсЂєсЂфсѓЅсђЂУ║ФСйЊсЂїсЂцсЂёсЂдТЮЦсѓІсѓѕсЂєуњ░тбЃсѓњТЋ┤сЂѕсЂГсЂ░сЂфсѓЅсЂфсЂёсђѓтцюТЏ┤сЂІсЂЌсЂЌсЂду▓ўсѓІсЂЊсЂесЂїТЋгУЎћсЂфсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂт┐ЁУдЂсЂфсЂЊсЂесЂ«сЂЪсѓЂсЂФТЌЕсЂЈуюасѓісђЂТЌЕсЂЈУхисЂЇсѓІсЂ╗сЂєсЂїТЋгУЎћсЂДсЂѓсѓІта┤тљѕсѓѓсЂѓсѓІсђѓТђњсѓісЂФтІЮсЂцтіЏсЂ»сђЂТёЈт┐ЌсЂ«уѕєуЎ║сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂТђњсѓісЂїТ╣ДсЂЇСИісЂїсѓІтЅЇсЂФуЦъсЂ«тЅЇсЂИт┐ЃсѓњТ│есЂјтЄ║сЂЎу┐њТЁБсЂІсѓЅТЮЦсѓІсђѓУфўТЃЉсЂФтІЮсЂцтіЏсѓѓсђЂуъгжќЊсЂ«УІ▒жЏёуџёТ▒║ТќГсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсђїУфўТЃЉсЂФжЎЦсѓЅсЂфсЂёсѓѕсЂєсђЇтЅЇсѓѓсЂБсЂдуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсѓІтЈЇтЙЕсЂІсѓЅТЮЦсѓІсђѓ
сЂЋсѓЅсЂФсѓѓсЂєСИђсЂцсђЂсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ»тЁ▒тљїСйЊсЂ«У▓гС╗╗сѓњтЋЈсЂєсђѓуДЂсЂЪсЂАсЂ»Уф░сЂІсЂїт┤ЕсѓїсѓІсЂесђїсЂфсЂюсЂЮсѓЊсЂфсЂФт╝▒сЂёсЂ«сЂІсђЇсЂетЋЈсЂёсЂїсЂАсЂасЂїсђЂудЈжЪ│ТЏИсЂ»сЂЮсѓїсѓѕсѓітЁѕсЂФсђїсЂфсЂютЁ▒сЂФуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсЂфсЂІсЂБсЂЪсЂ«сЂІсђЇсЂетЋЈсЂєсђѓт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїУфъсѓІтљїС╝┤сЂесЂ»сђЂсЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂФуЏИС║њУ▓гС╗╗сЂ«С┐АС╗░сЂДсЂѓсѓІсђѓУф░сЂІсЂФсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«тцюсЂїжќІсЂІсѓїсѓІсЂесЂЇсђЂсЂЮсЂ«тѓЇсѓЅсѓњт«ѕсѓІт░ЈсЂЋсЂфУАїуѓ║РђћРђћСИђуињсЂФт║ДсЂБсЂдсЂёсЂдсЂѓсЂњсѓІсЂЊсЂесђЂуЪГсЂЈсЂДсѓѓуЦѕсЂБсЂдсЂѓсЂњсѓІсЂЊсЂесђЂТЋ┤сЂБсЂЪСИђУеђсЂДсЂЮсЂЊсЂФт▒ЁуХџсЂЉсѓІсЂЊсЂеРђћРђћсЂїсђЂсЂЮсЂ«С║║сѓњућЪсЂІсЂЎсђѓсѓцсѓесѓ╣сЂ»ухљт▒ђуІгсѓісЂДУАїсЂІсѓїсЂЪсЂїсђЂсЂЮсЂ«Тќ╣сЂ«ТЋЎС╝џсЂ»сђЂсѓѓсЂєсЂЊсѓїС╗ЦСИісЂЮсЂєсЂЋсЂЏсЂдсЂ»сЂфсѓЅсЂфсЂёсђѓС╗іТЌЦсђЂуДЂсЂЪсЂАсЂїС║њсЂёсЂ«сѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂДуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсѓІсЂесЂЇсђЂуДЂсЂЪсЂАсЂ»тЇЂтГЌТъХсЂ«тГцуІгсѓњт░ЉсЂЌсЂДсѓѓУ╗йсЂЈсЂЎсѓІтЁ▒тљїСйЊсЂесЂфсѓІсђѓ
сЂЊсЂ«тю░уѓ╣сЂДУіИУАЊсЂ»сђЂсѓѓсЂєСИђт║дТи▒сЂёжђџУи»сѓњжќІсЂёсЂдсЂЈсѓїсѓІсђѓсѓцсѓ┐сЃфсѓбсЃ╗сЃФсЃЇсѓхсЃ│сѓ╣сЂ«ућ╗т«ХсѓбсЃ│сЃЅсЃгсѓбсЃ╗сЃъсЃ│сЃєсЃ╝сЃІсЃБсЂ«сђјThe Agony
in the GardenсђЈ№╝ѕу┤ё1455сђю1456т╣┤№╝ЅсЂ»сђЂсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«тцюсѓњсђЂтй╝уЅ╣ТюЅсЂ«уАгУ│фсЂфуГєУЄ┤сЂДУдќУдџтїќсЂЌсЂдсЂёсѓІсђѓуххсЂ«СИГсЂДсѓГсЃфсѓ╣сЃѕсЂ»т▓ЕсЂ«сѓѕсЂєсЂфтю░тйбсЂ«СИісЂФуІгсѓісЂ▓сЂќсЂЙсЂџсЂЇсђЂжЂасЂЈсЂДсЂ»сЃдсЃђсЂїтЁхсЂЪсЂАсѓњујЄсЂёсЂдУ┐ЉсЂЦсЂЇсђЂСИІсЂДсЂ»сЃџсЃєсЃГсЃ╗сЃцсѓ│сЃќсЃ╗сЃесЃЈсЃЇсЂїуюасЂБсЂдсЂёсѓІсђѓсЃъсЃ│сЃєсЃ╝сЃІсЃБсЂ»тЇўсЂФтЄ║ТЮЦС║ІсѓњтєЇуЈЙсЂЎсѓІсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂсђїУиЮжЏбсђЇсѓњжЁЇуй«сЂЎсѓІсђѓтцЕсЂетю░сђЂсѓцсѓесѓ╣сЂет╝ЪтГљсђЂуЦѕсѓісЂеТГдтЎесђЂуЏ«УдџсѓЂсЂеуюасѓіРђћРђћсЂЮсЂ«жџћсЂЪсѓісЂїућ╗жЮбтЁеСйЊсѓњТћ»жЁЇсЂЎсѓІсђѓсЂЮсЂ«жџћсЂЪсѓісЂ»сђЂт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїУфъсѓІсђїтГцуІгсЂфтЇЂтГЌТъХсЂИсЂ«жЂЊсђЇсѓњУдќУдџУеђУфъсЂИу┐╗Уе│сЂЌсЂЪсЂІсЂ«сѓѕсЂєсЂасђѓуДЂсЂЪсЂАсЂ»сЂЮсЂ«уххсЂ«тЅЇсЂДсђЂсђїУЄфтѕєсЂ»сЂЕсЂЊсЂФуФІсЂБсЂдсЂёсѓІсЂ«сЂІсђЇсЂетЋЈсѓЈсЂЋсѓїсѓІсђѓсѓцсѓесѓ╣сЂ«уЦѕсѓісЂ«тѓЇсЂІсђЂсЂЮсѓїсЂесѓѓуюасѓісЂ«т«ЅТЦйсЂ«СИГсЂІсђЂсЂѓсѓІсЂёсЂ»УБЈтѕЄсѓісЂ«УАїтѕЌсЂ«СИГсЂІсђѓ
сЃъсЃ│сЃєсЃ╝сЃІсЃБсЂ«уххсѓњТћ╣сѓЂсЂдТђЮсЂёУхисЂЊсЂЎсЂесђЂСИІсЂДуюасѓІт╝ЪтГљсЂЪсЂАсЂ»сђЂтЇўсЂфсѓІТђаТЃ░сЂфС║║сђЁсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂуДЂсЂЪсЂАсЂїу╣░сѓіУ┐ћсЂЎТѓ▓тіЄуџёсЃЉсѓ┐сЃ╝сЃ│сѓњС╗БУАесЂЌсЂдсЂёсѓІсђѓуДЂсЂЪсЂАсЂ»ТёЏсЂЎсѓІС║║сЂ«сЂЪсѓЂсЂФсђїСйЋсЂДсѓѓсЂЎсѓІсђЇсЂеУеђсЂёсЂфсЂїсѓЅсђЂсЂёсЂќсЂЮсЂ«С║║сЂїТюђсѓѓт╝▒сЂЈсЂфсЂБсЂЪтцюсЂФсЂ»сђЂжџБсЂФт║ДсЂБсЂдсЂёсѓІтіЏсЂїсЂфсЂёсђѓсЂасЂІсѓЅуххсЂ«УиЮжЏбТёЪсЂ»сђЂУЄфти▒тФїТѓфсЂДухѓсѓЈсЂБсЂдсЂ»сЂфсѓЅсЂфсЂёсђѓУиЮжЏбТёЪсЂ»ТѓћсЂёТћ╣сѓЂсЂ«Тќ╣тљЉсѓњуц║сЂЎсђѓуДЂсЂЪсЂАсЂ»сѓцсѓесѓ╣сЂ«тѓЇсЂИсђЂуЦѕсѓісЂ«та┤сЂИсђЂсђїуЏ«сѓњУдџсЂЙсЂЌсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесђЇсЂ«т«ЪУихсЂИсђЂСИђТГЕуД╗сѓІсЂ╣сЂЇсЂасђѓсЂЮсЂ«СИђТГЕсЂ»тцДсЂњсЂЋсЂДсЂѓсѓІт┐ЁУдЂсЂ»сЂфсЂёсђѓСИђТЌЦсЂФ10тѕєсЂДсѓѓжЮЎсЂІсЂФт║ДсЂБсЂдсђїсѓбсЃљсђЂуѕХсѓѕсђЇсЂетЉ╝сЂХсЂЊсЂесђѓсЂЮсЂ«ТЌЦсЂ«ТЂљсѓїсЂеТг▓ТюЏсѓњжџасЂЋсЂџТГБуЏ┤сЂФти«сЂЌтЄ║сЂЎсЂЊсЂесђѓсЂЮсЂЌсЂдТюђтЙїсЂФсђїсЂѓсЂфсЂЪсЂ«тЙАт┐ЃсЂ«сЂЙсЂЙсЂФсђЇсЂесЂёсЂєСИђТќЄсЂДсђЂт┐ЃсЂ«тљЉсЂЇсѓњтЏ║т«џсЂЎсѓІсЂЊсЂесђѓсЂЮсѓїсЂЊсЂЮсЂїсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«уЦѕсѓісѓњС╗іТЌЦсЂ«УеђУЉЅсЂДсЂцсЂфсЂјуЏ┤сЂЎсђЂТюђсѓѓуЈЙт«ЪуџёсЂфС╗ЋТќ╣сЂДсЂѓсѓІсђѓ
ухљт▒ђсђЂт╝хсЃђсЃЊсЃЄуЅДтИФсЂїсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂДуДЂсЂЪсЂАсЂФУдІсЂЏсѓѕсЂєсЂесЂЎсѓІсЂ«сЂ»сђЂсђїУІдсЂЌсЂ┐сђЇсЂЮсЂ«сѓѓсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂУІдсЂЌсЂ┐сЂ«СИГсЂДсѓѓтѕЄсѓїсЂфсЂёжќбС┐ѓсЂ«у┤љсЂДсЂѓсѓІсђѓтЇЂтГЌТъХсЂ»сѓцсѓесѓ╣сЂ«ућЪТХ»сЂФуфЂуёХуЈЙсѓїсЂЪТѓ▓тіЄсЂДсЂ»сЂфсЂёсђѓТёЏсЂ«СИђУ▓ФТђДсЂїТюђтЙїсЂЙсЂДТі╝сЂЌжђџсЂЋсѓїсЂЪта┤ТЅђсЂДсЂѓсѓІсђѓсЂЮсЂ«СИђУ▓ФТђДсЂїсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂДуЦѕсѓісЂесЂЌсЂдтйбСйюсѓЅсѓїсђЂжђ«ТЇЋсЂ«уъгжќЊсЂФсѓѓТЈ║сѓІсЂїсЂфсЂётцДУЃєсЂЋсЂесЂЌсЂдуЈЙсѓїсђЂсЂцсЂёсЂФсѓ┤сЃФсѓ┤сЃђсЂДУЄфтѕєУЄфУ║Фсѓњти«сЂЌтЄ║сЂЎУ┤ѕсѓіуЅЕсЂесЂЌсЂдт«їТѕљсЂЎсѓІсђѓсѓєсЂѕсЂФтЈЌжЏБу»ђсЂ«ж╗ЎТЃ│сЂ»сђЂТ▓ѕсѓЊсЂаТёЪТЃЁсЂФуЋЎсЂЙсѓЅсЂфсЂёсђѓсѓђсЂЌсѓЇТюђсѓѓТџЌсЂётцюсѓњжђџжЂјсЂЌсЂЪтЙЊжаєсЂїсђЂсЂЕсѓЊсЂфТюЮсѓњжќІсЂЈсЂ«сЂІсђѓсЂЮсЂ«ТюЮсЂїсђїтЙЕТ┤╗сђЇсЂесЂёсЂєтљЇсЂДсђЂсЂЕсЂ«сѓѕсЂєсЂФуДЂсЂЪсЂАсѓњсѓѓсЂєСИђт║дућЪсЂІсЂЎсЂ«сЂІсѓњУдІсЂцсѓЂсЂЋсЂЏсѓІсђѓсЂЮсЂЌсЂдтЙЕТ┤╗сЂ«тЁЅсЂ»сђЂсѓ▓сЃЃсѓ╗сЃъсЃЇсЂ«тюДсЂЌТй░сЂЌсѓњУдІсЂфсЂёсЂхсѓісѓњсЂЌсЂфсЂІсЂБсЂЪС║║сЂФсЂісЂёсЂдсђЂсЂёсЂБсЂЮсЂєж««ТўјсЂФтЈЇт░ёсЂЎсѓІсђѓ
ТЌЦТюгсѓфсЃфсЃЎсЃЃсЃѕсѓбсЃЃсѓ╗сЃ│сЃќсЃфсЃ╝ТЋЎтЏБ