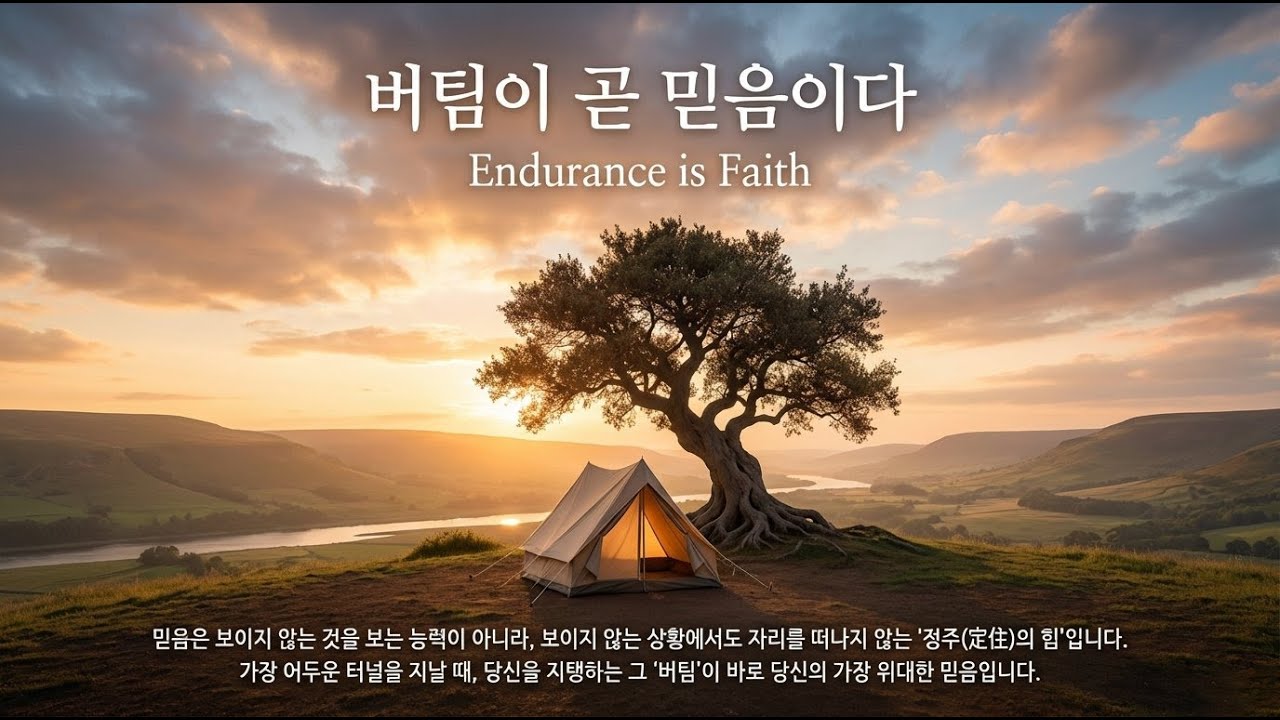張ダビデ牧師が、創世記1〜11章の「原始史」を中心軸として、人間の堕落とサタンの策略、そして神の裁きと救いの計画を精緻に解き明かしつつ、今日を生きる信徒がどのように罪と誘惑を見分け、神の子として回復されたアイデンティティを生きることができるのかを、神学的な洞察と霊的な省察の中で深く論じた文章である。
張ダビデ牧師は、聖書を読む入口として、創世記1章から11章までを「原始史」と呼ばれる一つの大きな物語単位として見渡さなければならないと強調する。比較的短いこの区間の中に、創造と堕落、裁きと救い、人類の系図と歴史の行方が凝縮されたかたちで配置されているからである。創世記1〜2章は創造の序曲を、3〜4章は人間の堕落と罪の発生を、5章は系図の流れを、6〜7章は洪水の裁きを、そして続く諸章は新しい救いの軌跡を提示する。張ダビデ牧師は、このような原始史が単なる古代伝承の寄せ集めではなく、人類全体を貫く神学的な原型(アーキタイプ)であると解釈する。イエスが「ノアの日に起こったことは、人の子の日にも同じように起こる」と語られた御言葉(ルカ17:26)に照らして見れば、終わりの裁きと救いのパターンを理解するためには、ノアの日、すなわちこの原始史の構造を深く思い巡らさなければならないというのである。
その中でも、創世記3章は人間の堕落の本質とプロセスを明らかにする中核テキストとして位置づけられる。張ダビデ牧師は、エデンの園に登場する蛇を単なる象徴的な動物ではなく、神に反逆した霊的存在、すなわちサタンの道具であり表現であると読み解きつつも、同時に聖書は決して善と悪という二つの原理が対等に対立する二元論を語ってはいないことを強調する。「主なる神が造られた野の生き物のうちで、蛇が最も狡猾であった」という一節は、サタンさえも被造物の地位に置かれていることを思い起こさせる。初めから神とサタンという二人の絶対者が互角に戦っている構図ではなく、主権者である神が造られた世界の中で、一つの被造物が高慢によって堕落した出来事なのだ、ということである。
張ダビデ牧師は、サタンの堕落の深層原因を「自己高揚の高慢」と規定する。神と張り合おうとする欲望、神と同じ座を狙う内的衝動こそ、すべての罪の根源だと分析するのである。この点で彼は自然にピリピ人への手紙2章を想起する。堕落した霊的存在が自己誇示と自己拡大によって崩れ去ったのに対し、神の御子はむしろご自分を空しくし、しもべの姿を取られた。ケノーシス(kenosis)、すなわち自己を無にし、自ら進んで低くなられるキリストの道は、サタンの道と本質的に正反対の軌跡である。張ダビデ牧師の解釈によれば、まさにこの謙遜と従順の道を通してサタンはすでに裁きを受け、罪と死が支配していた秩序は根本から覆されたのだという。
多くの人が神義論的な問いを投げかける。「もし神が全能なら、そもそもアダムとエバが善悪の知識の木の実を食べられないように設計すればよかったのではないか。なぜ倒れる可能性のある構造をお許しになったのか」と。張ダビデ牧師は、この問いが神学における古くからの難問であることを認めつつも、その答えの中心には「愛」というテーマが置かれていると説明する。神は人間に「生めよ、増えよ」(Be fruitful)と命じられた。この「実を結ぶ」という言葉は、単なる人口増加を意味しない。愛の一致が完成した状態、すなわち「その日には、わたしが父のうちに、あなたがたがわたしのうちに、わたしがあなたがたのうちにいることを知る」(ヨハネ14:20)という関係の成熟を指し示している。愛は強制によって生み出すことはできず、リモコンで操られるかのように動く存在からは、決して真実の愛は咲き出てこない。全能の神が人間を、操りやすい人形ではなく、自由意志によって愛を選ぶことのできる人格的存在として造られたのは、危険を覚悟した決断というよりも、むしろ創造の栄光と愛の尊さを現わす宣言なのだ、というのである。
この論理は天使たちにも拡張される。ユダの手紙1章は、ある天使たちが自分の地位を守らず、自分の住まいを離れて神に反逆した結果、「大いなる日の裁きまで、永遠の鎖で暗闇に閉じ込められた」と証言している。見えない霊的存在でさえ、自由意志を持つ被造物として、従順と反逆を選ぶことができ、その責任を免れることはできなかったという意味である。張ダビデ牧師は、ここに重要な神学的バランスがあると指摘する。問題の根源は神にあるのではなく、善きものとして与えられた自由を誤用した被造物側にある。神は悪の設計者ではなく、悪によって痛み、嘆かれる被害者であられる。ゆえに、「神が世界を間違って造ったからこのような悲劇が起きたのだ」といった責任転嫁は、創造主に対する重大な誤解であり、別の形の反逆であると彼は警告する。
創世記3章に登場する蛇の最初の発言は、神の言葉に対するあからさまな挑戦である。神が「取って食べるなら、必ず死ぬ」とはっきり警告されたにもかかわらず、蛇は「決して死ぬことはない」と真っ向から反対の宣言をする。張ダビデ牧師は、この短い一文の中にサタンの戦略が凝縮されていると見る。まず神の言葉に疑念を抱かせ、真理に対する信頼を揺るがし、そのうえで真理を偽りに、偽りを真理に逆転させるのである。しかし、単なる論理的反論だけでは人間の心を完全につかむことは難しい。そこでサタンは、そこに甘い誘惑と微妙な嫉妬心を巧みに混ぜ合わせる。「神は、あなたがたが神のようになり、善悪を知るようになることを知っておられる」というささやきは、神を愛の創造者ではなく、良いものを独占しようとする存在として歪め、人間の内側にひそやかな反抗心と落ち着かない不信を育てていく。
張ダビデ牧師は、罪を犯した存在の特徴を「一緒に堕落させようとする衝動」と診断する。自ら罪を犯した後、深い不安に陥った心は、責任を一人で負うよりも、他の人々を巻き込み、罪を正常なもの、集団的なものとしてしまうことで不安を鎮めようとする。だからサタンは執拗に人間を誘惑し、「一緒に滅びよう」という心境で罪の集いを広げていく。黙示録が「天の星の三分の一が落ちた」と描写するとき、張ダビデ牧師はこれを、サタンが他の天使たちまで惑わして堕落させた出来事を象徴的に表していると読み解く。今日の文化全般において、歪んだ価値観と罪が構造化され、さまざまなコンテンツや世論を通して繰り返し再生産されている現象も、同じ霊的原理の上に立っていると解釈するのである。
もう一つ重要な洞察は、エデンにも明確な戒めが存在していたという事実である。人々は時に、天国をあらゆる制約がない自由空間のように想像するが、聖書はそう語らない。善悪の知識の木に関する禁令は、創造主であり絶対主権者である神が人間に与えられた明確な境界線であった。天国とは、「したいことを何でもしてよい場所」ではなく、愛のうちに自発的に神の御心に従う秩序の世界である。戒めが存在するということは、愛が損なわれている印ではなく、愛がどのように具体的に表現され、守られるべきかを示す柵なのだ。
しかし、蛇の視点から見ると、この戒めは抑圧の象徴として映る。そこでサタンは、「なぜ神だけが善と悪を定める最終基準でなければならないのか。おまえもその座に就くことができる」というささやきを吹き込む。張ダビデ牧師にとって、これこそが高慢の核心である。何が善で何が悪か、何が真で何が偽かを最終的に判断できるのはただ神だけであるのに、その座を被造物が奪い、自ら善悪の根源的基準になろうとする瞬間に、堕落の門が開かれるのである。現代社会で「それぞれが自分で善悪を決めればよい」「絶対的真理は存在しない」といったスローガンが魅力的に聞こえる理由もここにある。自由という名のもとに善悪の基準そのものを解体してしまえば、やがて世界全体が相対主義と極端な自己中心性の洪水の中に沈み込んでしまう。
では、具体的に堕落はどのような過程をたどるのか。張ダビデ牧師は、「女がその木を見ると、それは食べるのによく、目に麗しく、賢くしてくれそうに慕わしい木であった」という一節に注目する。この短い表現の中に、誘惑の典型的な三段階が含まれている。まず目で見(目の欲)、心で欲しがり(肉の欲)、ついには手を伸ばして取る行為が続く(暮らし向きの誇り)。ヨハネの第一の手紙2章が説明する世の欲の構造が、創世記の本文の中で物語として再現されているわけである。今日の性的誘惑や物質主義的誘惑も同じ経路をたどる。映像やイメージが視線を奪い、想像力と欲望を刺激し、やがて行動と習慣へと固まっていく。だからこそ張ダビデ牧師は、何よりも「何を見るのか」に気をつけるよう勧める。罪はすでに戸口でうずくまり、私たちが顔をのぞかせるとすぐにでも捉えようと待ち構えているのである(創世記4:7)。
創世記4章でカインが弟アベルをねたみ、ついには殺害に至る過程も、同じ構造に従っている。神がアベルのささげ物だけを受け入れられたとき、カインは驚きと恐れのうちに恵みを悟るべきであった。罪人のささげ物が受け入れられたという事実そのものが、すでに過分な恩寵だからである。ところがカインは、神の恵みを喜びと感激ではなく、怒りと傷として受け止め、その中で育った嫉妬とねたみが、ついには殺人の罪へとつながっていく。張ダビデ牧師はこれを、人間の罪性の核心である「自己中心性(エゴセントリズム)」として分析する。自分を基準に神と他者を評価し、恵みの前でさえ「なぜ自分はもっと認められないのか」と問う姿勢こそが、罪の深淵なのだという。
かといって、人間が完全に闇としてだけ規定されるわけではない。張ダビデ牧師は、「二人の目が開かれ、自分たちが裸であることを知った」という表現に、人間存在の独特な両面性が現れていると見る。罪を犯した瞬間、人間はそれが間違いであることを直感的に知る。羞恥心と恐れが押し寄せ、いちじくの葉で慌てて自分を覆おうとする。動物は恥を知らず、本能のままに生きるが、人間は真理から離れるとき、存在論的な恥と実存的な不安を経験するように造られている。これは、人間の魂の奥深くに神へと向かう本能的な方向性が刻み込まれているしるしである。ひまわりが太陽の方へ向きを変えるように、人間の魂は本来、創造主の方へと傾いている。罪はこの方向を歪め、ぼやけさせるが、その内的な刻印を完全に消し去ることはできない。
いちじくの葉を編んで作った衣は、人間の自己義認を象徴するイメージとして読むことができる。人は自分の罪を隠すために、道徳や宗教、体面や業績という葉を慌ただしく編んで腰に巻くが、神の前では依然として裸の存在であることを免れない。驚くべきことは、神がこのようなアダムとエバをすぐさま滅ぼしてしまわれるのではなく、かえって革の衣を作って着せられたという事実である。張ダビデ牧師は、この場面を「先取りされた恵みのしるし」と解釈する。誰かの血の流しと犠牲を前提にして初めて手に入る革の衣は、のちにキリストの十字架において完成する贖いと義の衣をあらかじめ示す予表である。罪ゆえに恥と恐れの中に身を隠した人間に対して、神は先に近づいてこられ、「あなたはどこにいるのか」と呼びかけ、その恥を覆ってくださるのである。
ここで張ダビデ牧師は、神の御声のニュアンスをとりわけ強調する。「あなたはどこにいるのか」という言葉は、怒りに満ちた叱責ではなく、打ち砕かれた魂を探し出そうとされる、切なる愛の呼びかけである。この問いこそが、救いの出発点である。神は罪人に向かって、まず「なぜそんなことをしたのか」と詰問されるのではなく、「今どこにいて、なぜわたしを避けているのか」と問われる。今日を生きる信徒に対しても、この問いはなお有効である。夜の間に蛇の誘惑に負けて心が崩れてしまったとしても、朝になって再び神の御前に出て、「主よ、ここにおります」と答えることが、回復への第一歩なのだと、張ダビデ牧師は勧める。
しかし、堕落の物語で最も痛ましい場面は、アダムの最初の答えの中に見出される。「わたしと一緒にいるようにしてくださったあの女が、あの木から取ってくれたので、わたしは食べました」。張ダビデ牧師は、この一言に、罪のもう一つの本質である責任転嫁が赤裸々に現れていると見る。アダムは自分の罪を正直に認めるのではなく、女を責め、さらに「わたしと一緒にいるようにしてくださった女」という言い回しを通して、さりげなく神に責任を押しつける。一方、新約でバプテスマのヨハネはイエスを指して、「世の罪を取り除く神の小羊」と宣言する。アダムは罪を他人に押しつけ、キリストは他人の罪を自分に引き受けられた。この鮮やかな対比の中に、救いの歴史の方向性がはっきりと見えてくる。
張ダビデ牧師は、イエスに似るということは、結局この方向転換を意味すると説明する。「おまえのせいだ」と叫んでいた唇が、「わたしのせいです、わたしの大きな罪です」と告白する唇へと変えられていくこと、他人に重荷を押しつけていた人が、「互いの重荷を負い合いなさい」(ガラテヤ6:2)という御言葉に従って、他者の重荷を共に負う人へと変わっていくこと、これがキリストの弟子のしるしである。古くからの伝統教会でささげられてきた「わたしのせいです、わたしの大きな罪です」という悔い改めの祈りも、同じ霊的原理の上に立っている。イエスがゲツセマネの園で「わたしの望むようにではなく、御心のままになさってください」と祈り、人類の罪を背負われたように、その方に従う弟子たちもまた、自己中心性の回路を断ち切り、責任を引き受ける愛の道へと召されているのである。
これらすべての物語的な流れの背後には、目に見えない霊的戦争が展開されている。ヨブ記には、サタンが神の御座の前に進み出て、ヨブを告発する場面が描かれている。「この人が神を恐れているのは、あなたが柵で守っているからであって、本当の畏れではない」といった嘲り混じりの論法である。張ダビデ牧師は、これを「誰が誰を支配する資格を持つのか」をめぐる宇宙的論争として理解する。創世記3章の堕落の場面でも、サタンは事実上、神に向かってこのように語っていることになる。「ご覧にならなかったのですか。この人間たちは、自分を支配する資格がありません。むしろ私が彼らを支配すべきです」。神はこの挑戦に対し、最後のアダム、すなわちイエス・キリストをお遣わしになることで応答されたのである。
マタイによる福音書4章で、イエスは荒野で三度の試みに遭われるが、すべて記された御言葉で応答して勝利される。生存をめぐるパンの試み、宗教的誇示と安全をめぐる神殿の頂の試み、栄光と権勢をめぐる絶対的忠誠の試みに至るまで、すべてに打ち勝たれて初めて、悪魔は去り、天使たちが来て仕える。張ダビデ牧師は、これがヘブライ人への手紙1章が語る創造の秩序、すなわち「すべての天使は、救いを受け継ぐ者たちに仕えるために遣わされた奉仕する霊である」という宣言が、歴史の中で具体化した場面であると解釈する。最初のアダムは蛇の前で倒れたが、最後のアダムであるキリストはサタンを屈服させ、失われた創造の秩序を取り戻されたのである。
再び創世記3章14〜15節に目を向けると、この短い本文の中に、罪と裁き、そして救いの約束が高密度に凝縮されていることに気づく。神はまず蛇に向かって、「おまえはすべての家畜、野のすべての獣よりも、のろわれる。腹ばいで歩き、一生、ちりを食べる」と宣言される。張ダビデ牧師は、この一節を通して、「他者を罪に陥れる者への裁き」がいかに厳しいかを思い起こさせる。イエスもまた、他の人をつまずかせる者は、いっそ首に石臼をかけて海に投げ込まれるほうがましだと言われた。誘惑をあおる文化、罪を促す構造、他者を転ばせる言葉と行いは、すべて神の前で重い責任を問われることになる。
しかし同時に、神は裁きの言葉だけを残されるのではない。「わたしはおまえと女との間に、またおまえの子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はおまえの頭を砕き、おまえは彼のかかとを砕くようになる」。張ダビデ牧師は、教会の伝統がこの節を「原始福音」と呼んできた理由に従い、これを聖書全体に現れる最初の福音の約束として読む。アダムにおいて人類全体が総崩れとなったが、神は新しい種、新しい人類の頭となる方を予言されたのである。女の子孫として来られるキリストは、十字架においてかかとを砕かれる苦しみを味わわれるが、その血潮によってサタンの頭を踏み砕く決定的勝利を成し遂げられる。ローマ人への手紙5章は、「一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の人の従順によって多くの人が義人とされる」と、この救済史的真理を鮮やかに宣言している。
この時点で張ダビデ牧師は、信徒のアイデンティティの回復というテーマへと視線を移す。信徒はもはや恐れと恥に縛られた奴隷ではなく、イエス・キリストにあって養子の霊を受けた神の子どもである。ローマ人への手紙8章は、「わたしたちは養子の霊を受けたので、『アッバ、父よ』と叫ぶ」と証言する。ヨハネによる福音書1章は、「この方を受け入れた人々、つまりその名を信じる人々には、神の子どもとされる特権が与えられた」と宣言する。義認とは、単なる感情的慰めのレベルではなく、法的・身分的転換の出来事である。罪人の座から子の座へと移される瞬間、存在の身分が変わり、それに見合う権威と責任が与えられる。その責任の重要な一部が、サタンの偽りを見分け、もはやその偽りに引きずられることなく、キリストにあって支配する生き方をすることである。
最後に張ダビデ牧師は、これらすべてのメッセージが夫婦と家庭、そして教会共同体の中でどのように具体化されうるのかを指し示す。アダムとエバの物語は、遠い昔のある夫婦の逸話ではなく、今日の私たち一人ひとりの関係を映し出す鏡である。互いに配偶者のせいにして罪と傷へ追い込む関係ではなく、相手の重荷を共に負い、「わたしのせいだ」と先に告白する関係こそ、天国の秩序に近い家庭である。現代文化は境界を取り払い、快楽と自己実現を絶対的善として包装し、「真理などない。各自思うままに生きればよい」とささやくが、聖書ははっきりと語る。真理は存在し、善と悪は区別され、神の言葉がその最終基準であるという事実である。
創世記1〜11章の原始史は、人類の遠い過去を説明すると同時に、私たちの現在を映す鏡であり、やがて来る未来を告げる予言的パターンでもある。ノアの日にそうであったように、人々が食べたり飲んだり、嫁いだり娶ったりする日常にのみ没頭し、堕落の深さを感じ取れない時代であればあるほど、神の言葉と裁き、そして救いの約束をいっそう深く握りしめなければならない。張ダビデ牧師は、創世記3章の物語を通して、私たちに根本的な問いを投げかける。「あなたは誰の声に耳を傾け、誰の言葉に従って生きているのか」。蛇の甘い嘘に従って「一緒に死のう」という道を進むのか、それとも「あなたはどこにいるのか」と呼ばれる神の愛の声に応えて、いのちの道へ立ち返るのか。
結局のところ、張ダビデ牧師の説教は一つの招きへと収束する。女の子孫であるキリストの十字架の下で、恥と恐れの古い衣を脱ぎ、神がくださる義と愛の新しい衣を着なさいという招きである。この呼びかけに応えた人は、もはや蛇の文化に流されることなく、原始福音が約束したとおり、蛇の頭を踏み砕く生き方、すなわちキリストの勝利にあずかる生き方へと召されていることを忘れてはならない。そしてその生き方は、日常のただ中で、家庭と職場と教会の中で、静かだが揺るがずに展開されていかなければならないのだと、張ダビデ牧師は重々しく語る。