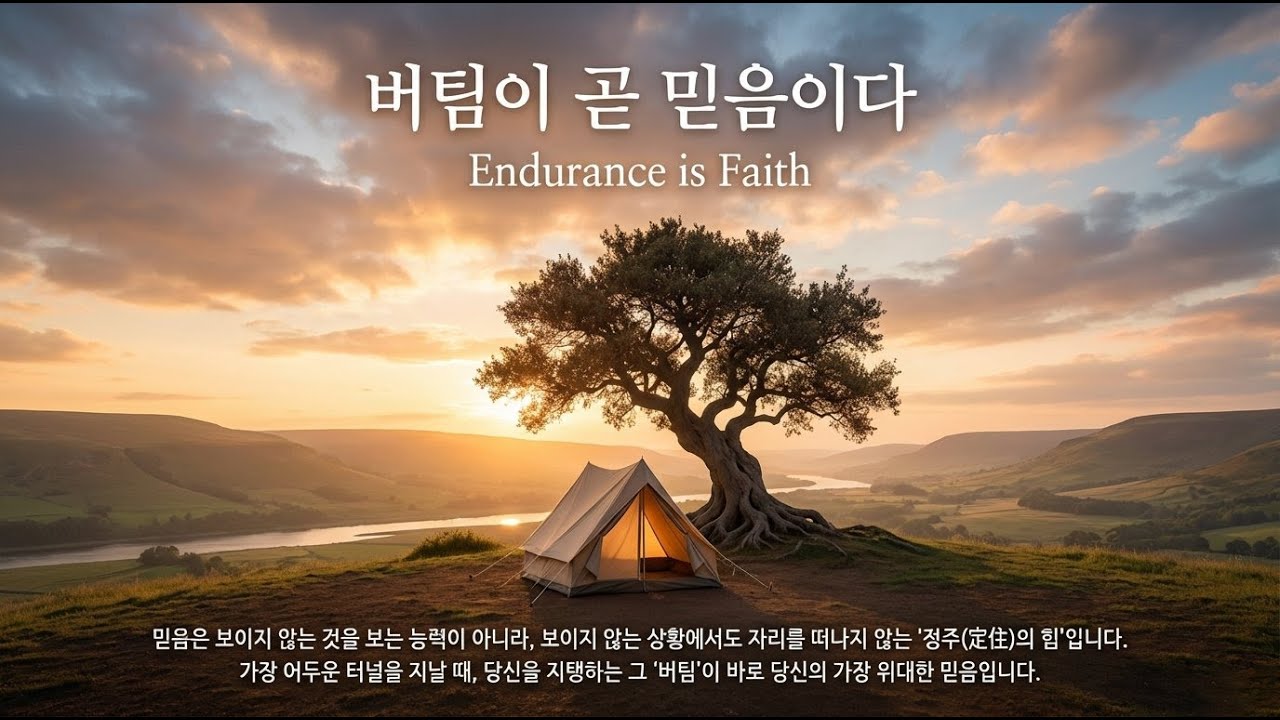マルコによる福音書14章の「香油の壺」の出来事を扱った張ダビデ牧師の説教を土台に、浪費のように見える愛の神秘とイスカリオテ・ユダの悲劇、イエスの葬りを備えたベタニアの女の献身を、神学・芸術・音楽・古典と結びつけて立体的に解き明かす。ベタニアの「らい病人シモンの家」から始まるこの物語を通して、今日の私たちの礼拝と献身、そして愛の本質をあらためて問い直す、深い霊性のエッセイである。
張ダビデ牧師の説教には、馴染み深い聖書箇所を思いもよらない角度から再び見させてくれるという独特の魅力がある。マルコによる福音書14章に記された香油の壺の出来事も、彼の手にかかると一つの短いエピソードではなく、時間と空間、人間の心理と霊的世界が綿密に織り込まれたドラマへと姿を変える。ベタニアのらい病人シモンの家、その家の中へ静かに入ってきて壺を打ち砕く一人の女、その光景を見て憤り計算を始める弟子たちとイスカリオテ・ユダ、そして最後に、この浪費を自らの葬りの準備であると宣言なさるイエスの御声が互いに交錯しながら、説教は自然に、今日を生きる私たちの信仰と生活に鋭い問いを投げかける。
物語の舞台は、エルサレムでの十字架の出来事をほんの数日後に控えたころ、小さな村ベタニアである。聖書はわざわざ、そこを「らい病人シモンの家」と、過去の傷を添えて呼ぶ。当時、らい病は社会的・宗教的隔離の象徴であった。共同体の外へ追いやられ、愛と触れ合いから排除されていたその人のところへ、イエスご自身が訪ねて来られ、その家の食卓で共に食事をなさる。張ダビデ牧師は、この短い表現の中に福音の心臓部を見る。愛を知らなかった魂が癒やしを経験し、今や感激の宴を催す場へと変えられたのである。シモンの家はもはや穢れた者の空間ではなく、恵みを受けた者が感謝の食卓を整える聖なる現場となる。
ちょうどその食卓のただ中に、名も知られぬ一人の女が入ってくる。マルコによる福音書は彼女を匿名のまま残しているが、ヨハネによる福音書はその女がラザロの姉妹マリアであると明かす。四つの福音書はいずれも、イエスに香油を注ぐ女の物語を、それぞれ少しずつ異なる角度から伝えている。マタイとマルコは、ベタニアのシモンの家で、イエスの頭に香油を注ぐ場面を描き、ルカは罪深い女がファリサイ人の家でイエスの足に香油と涙を注ぐ物語を語り、ヨハネは、ベタニアのマリアがイエスの足を香油でぬらし、自分の髪でそれをぬぐう場面を記している。時間も場所も異なりながら、どの場合も中心にあるのは「高価な香油」と「浪費のように見える愛」である。張ダビデ牧師は、こうした福音書の多声的な響きを背景に、マルコ14章の出来事を精緻に見つめていく。
女が手にしてきたのは、純粋なナルドの香油が入った一つの石膏の壺である。ナルドはヒマラヤ周辺から輸入されていた高価な香料で、一般家庭ではとても手を出せない贅沢品に近かった。福音書の表現どおり、この香油は三百デナリ以上の価値があり、デナリが当時の一般労働者の一日分の賃金であったことを考えると、安息日や祭日を差し引いても、ほぼ一年分の給料に相当する大金であったと解釈される。女はこの貴重な品を、少しだけ取り分けて使うようなことはしない。壺そのものを粉々に割り、香油のすべてをイエスの頭と足の上にいっきに注ぎかける。二度と元には戻せない決断、取り返しのつかない選択、自分の人生を通じて最も高価な一度きりの行為である。
張ダビデ牧師は、この壺を単なる高級化粧品としてではなく、女が一生握りしめてきた自分の存在と安全、そして未来全体の象徴として読み解く。パレスチナの文化では、尊い客人に香油を「少し」振りかけることは礼儀だったが、この女はその礼儀の線をはるかに越えてしまう。社会的常識や経済論理が制御できない領域、すなわち愛の過剰へと踏み込んでいくのである。その過剰ゆえに、その愛はただちに「浪費」という名を与えられる。弟子たちが憤りながら吐き出した言葉は、今日の私たちの耳にもなじみ深い。「なぜ、この香油をこんなにむだにするのか。三百デナリに売って貧しい人たちに施した方がよかったではないか。」彼らの言葉は一見、正義に満ち、倫理的で、経済感覚も優れているように聞こえる。だが説教者は、まさにここに弟子たちの霊的感覚が麻痺していることを見抜く。彼らの目には、イエスにささげられた愛の深さよりも、香油の値札の方が先に飛び込んできており、献身の香りよりも損得勘定の方が大きく迫っていたのだ。
ヨハネによる福音書は、この抗議の言葉を実際に口にした人物がイスカリオテ・ユダであったことを明らかにする。彼は「なぜ、この香油を三百デナリに売って貧しい人たちに施さなかったのか」と言うが、福音書は、彼が貧しい者たちを心から憐れんだからではなく、金入れを預かる盗人であったからだと冷静に解説する。ここに、女の愛とユダの計算との間にくっきりとした断層が生じる。張ダビデ牧師は、ヨハネ13章2節の「悪魔はすでにイスカリオテのユダの心に、イエスを売ろうとする思いを入れていた」という一節を重ね合わせながら、真実の愛があらわになる場を、かえって不快に感じて非難する心こそが、サタンが入り込むすき間なのだと指摘する。愛を愛として受け取れず、献身をただの浪費としか見られないその目が、ついにはユダを裏切りの座へと押しやっていくのだ。
この劇的な対比は、神学の世界を越えて、芸術と音楽の世界でも絶えず変奏されてきた。たとえばプラド美術館所蔵の17世紀のドローイング《Mary Magdalen at the Feet of Christ》を見ると、マグダラのマリアと思しき女が床にひざまずき、キリストの足に口づけしており、食卓の上座に座るイエスのかたわらには、驚きと不快感が入り混じった表情で手ぶりをしている人物たちが描かれている。罪深い女がイエスの足に涙と香油を注ぐルカ福音書の場面を視覚化したこの絵は、非難と軽蔑の視線を突き抜けて主だけを見つめる献身の姿勢を、濃密に浮かび上がらせる。現代のキリスト教画家たちが描く「イエスの足に香油を注ぐマリア」シリーズでも、イエスの足にすがってすすり泣く女と、その背後で顔をしかめて立っているユダの姿とが繰り返し対比され、愛と貪欲、礼拝と計算の衝突が強烈に表現されている。
音楽においても、この聖句は特別な重みを持っている。ヨハン・ゼバスティアン・バッハの《マタイ受難曲》は、マタイ福音書の受難物語を辿りながら、福音書のナラティヴと会衆の内的応答を交差させる偉大な信仰のオラトリオである。その構造を見ると、前半にベタニアでの香油の注ぎの場面が置かれ、続く合唱曲〈Wozu dienet dieser Unrat?〉(「この無駄遣いが何の役に立つのか」)で、合唱団は憤る弟子たちの声となってその不平を歌い上げる。続いて、福音書朗読者とイエスのレチタティーヴォが続き、イエスは「彼女は私の葬りのために、あらかじめ私を用意してくれた」と応答される。張ダビデ牧師が説教の中で強調するように、世と弟子たちの目には浪費と映る行為が、イエスの目にはご自身の死を備えた美しい献身として再解釈されるのである。バッハはこの神学的再解釈を、音の緊張と解消によって表現し、説教者はその解釈を、今日の私たちの礼拝と生活のただ中に引き寄せ、もう一度問いかけさせる。
張ダビデ牧師は、女の行動を単なる一瞬の感情の爆発とは見ず、イエスの死と葬りを直感した霊的直観の表現として読む。「彼女は私の葬りのために、あらかじめ用意してくれた」というイエスの言葉には、ご自身の生涯全体が結局は私たちへの愛の旅路であり、その旅路の終着点が十字架の死であるという事実が凝縮されている。香油は、死者の体を清め、最後に塗る香り高い敬意のしるしであった。女は、まだ十字架が起こる前に、自分に与えられるかもしれない最後の機会を前倒しにして、手元にある最も尊いものをあらかじめ取り出し、主の御身体の上に注ぎかける。愛する者の死を感じ取った人だけが選ぶことのできる、無謀とも言える行為である。この浪費はそのまま、十字架の上でご自身の体と血を「打ち砕かれ、注ぎ出される」愛として差し出されるイエスご自身の運命を、かすかに照らし出す予言的な身振りでもある。
このあたりで説教は自然に、ルカ15章の失われた羊とドラクマ、放蕩息子のたとえへと流れていく。九十九匹を野に残して一匹を捜しに出る羊飼いの行動、失われていた銀貨一枚を見つけたからといって隣人を呼び集めて宴会を開く女の喜び、財産を浪費しきって帰ってきた息子のために、最上の衣と指輪、肥えた子牛までも惜しみなく与える父の歓待――どれ一つとして、経済論理では説明できない。すべて非合理で非効率な愛である。だがイエスはためらうことなく、この非効率の頂点に立っておられる神を指し示される。愛はいつも計算を超えて溢れ、そのあふれ出る分がすなわち「無駄遣い」と映るのだ。張ダビデ牧師は、この無駄を取り除こうとしたのが弟子たちであり、今日の私たち自身でもありうると鋭く指摘する。責任感や効率性そのものが問題なのではなく、それらが愛よりも先に基準となってしまうとき、問題が生じるのだと。
彼はまた、今日の私たちの信仰が、どれほどたやすく「ユダ的合理性」に捕らわれてしまうかを冷徹に指摘する。礼拝の時間、献身の労苦、財政の用い方、働きの実りを語るとき、私たちは本能的に「効率」「成果」「投資対効果」といった言葉を取り出す。こうした言葉は、組織やプロジェクトを運営するうえでは必要だが、愛の領域にまで同じ物差しを当て始めるとき、礼拝はたちまち冷ややかな評価へと変質してしまう。張ダビデ牧師は、「愛が冷えれば冷えるほど、私たちはますます賢くなり、計算高くなる」と語り、賢さそのものよりも、愛を失った賢さがどれほど致命的であるかを警告する。女の行動は、確かに非合理的である。しかしその非合理性ゆえにこそ、イエスは「彼女は私に良いことをしてくれた」と宣言され、福音が宣べ伝えられるところではどこででも、この女のしたことも語られて、彼女の記念となるのだと約束される。
一方で、張ダビデ牧師の生涯そのものもまた、愛と構造、献身と制度とのあいだの緊張を物語っている。彼は韓国出身の神学者・牧会者として、アメリカのOlivet Universityをはじめ、いくつものキリスト教教育・宣教機関やメディア・ミニストリーを設立してきた。この経歴は、彼が愛を単なる熱い感情にとどめず、教育とメディア、宣教の構造を通して持続可能な献身として組織化しようとしてきたことを示している。それでもなお、今回の説教で彼が繰り返し強調する点は明確である。どのような制度や働きであっても、ベタニアの女が示した、あの無条件で無謀な愛の心臓部を失った瞬間に、ユダの計算と変わらない空しい殻になりうるのだということである。
今日の文化の中で、ベタニアの女の物語は、さまざまな芸術作品と霊性の伝統を通して、今もなお再解釈され続けている。イエスの油注ぎを主題とする聖画では、しばしば十字架の下にひざまずくマグダラのマリアのそばに、小さな香油の壺が描かれ、彼女を識別する象徴として用いられる。現代の礼拝音楽においても、『Alabaster Jar』『Alabaster Box』をはじめとする多くの楽曲が、「主に自分のすべてを注ぎ出したい」という告白を何度も歌い続ける。古典的な霊性家や説教者たちは、香油の香りを、砕かれ壊れた人生から流れ出る恵みの香りになぞらえてきた。人生が完璧なときではなく、壺が打ち砕かれるその瞬間にこそ、深い香りが広がっていくのだという洞察である。張ダビデ牧師の説教もまた、この伝統と共鳴しながら、その香りを抽象的な比喩ではなく、イエスと私たちとの具体的な関係の中に生き生きと蘇らせている。
結局、この聖句は私たち一人ひとりに一つの問いを投げかける。私はこの物語の中で、誰に似ているだろうか。壺を割って香油を注ぎ出す女か、それともそのそばで「なぜこんな無駄をするのか」と計算する弟子たちか、あるいは、心の奥底で愛の現場に居心地の悪さを覚え、ついには主のもとを去ってしまうユダか。張ダビデ牧師は、この問いを単なる道徳テストとして投げかけているのではない。それは、私が福音をどれほど深く受け入れているのか、そしてイエスの愛を抽象的な教理ではなく、現実の出来事として体験したのかどうかに関する霊的診断でもある。キリストの愛がなお観念の中にしかとどまっていないなら、他者の献身はいつも過剰に見え、ときには危険にさえ映る。しかし、十字架で最後まで私を愛し抜かれたその愛が、実際に私の内に住み始めるとき、私はますます愚かになる勇気を持ち始める。計算をやめ、自分の壺を打ち砕く勇気である。
最後に、説教は再び出発点へと戻っていく。イエスがらい病人シモンの家を訪ねられた愛、罪人である女を抱きしめ弁護された愛、最後まで弟子たちの席を空けておかれた愛。主の愛は、冷静な目で見れば、もしかするとすべてが浪費に見えるかもしれない。裏切る弟子たちのために涙ながらに祈り、逃げ去る群衆のために血を流し、背を向けてしまう人々のために最後まで待ち続ける愛だからである。だが、この浪費のような愛がなかったなら、私たちが福音を知る道はなかっただろう。そうだとすれば、問いは自然にこう変わる。「主が私のためにそこまで浪費してくださったのに、私はいったい何をそれほど惜しんで握りしめているのか。」時間か、財産か、体面と安全な未来か。ベタニアの女の物語は、結局、私たち一人ひとりが手に握っている壺は何なのか、そしてそれをいつ、主の前で打ち砕くのかを問いかける、静かでありながら決して避けることのできない招きなのである。
イエスはこう言われた。「世界中どこでも、この福音が宣べ伝えられるところでは、この女のしたことも語られて、この人の記念となるであろう。」この約束は、張ダビデ牧師のような説教者たちの唇を通して、またこの文章を読む人々の人生を通して、今もなお現在形で成就し続けている。香油の香りはすでにベタニアのシモンの家を満たしたが、今度は私たちの日常と人間関係、礼拝と献身のうちを満たそうとして待っている。愛を「無駄遣い」と呼ばない人、むしろ喜びをもって無駄を選び取る人――そうした人々が集う場所こそが真の教会であり、彼らの生き方そのものが、世に差し出される最も説得力ある福音の証しとなるだろう。
Olivet Assebmly of Japan