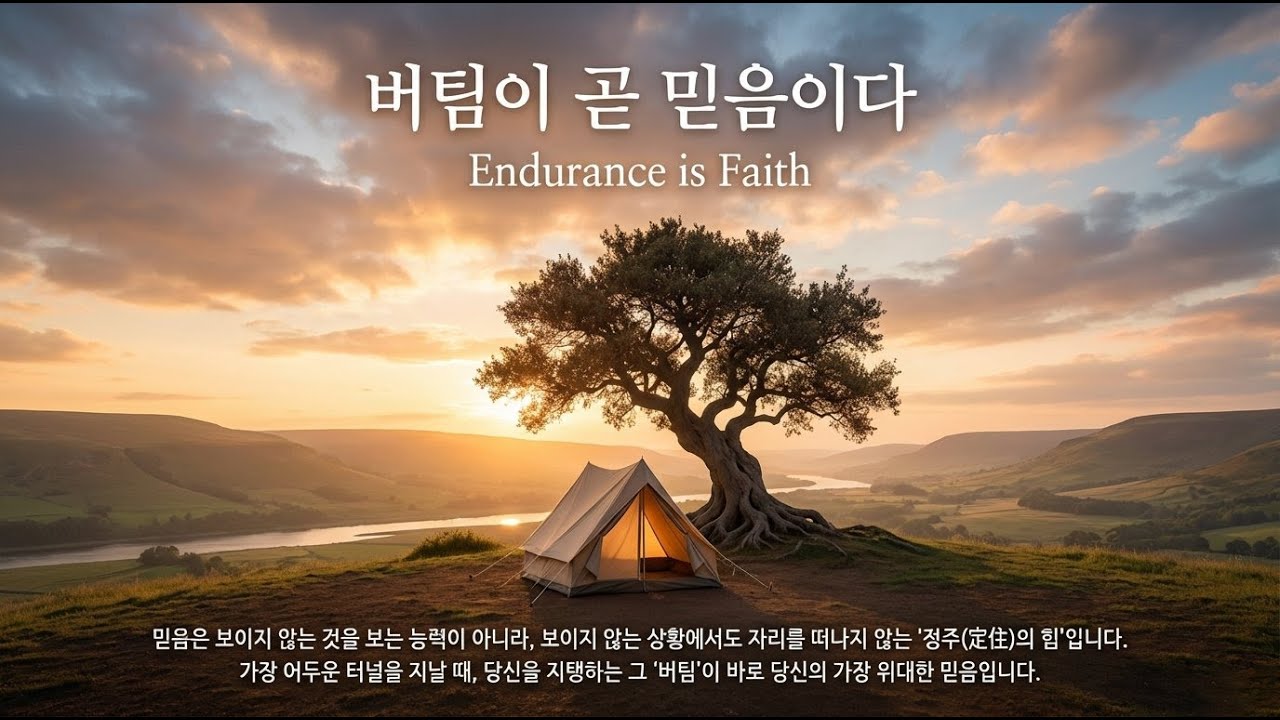ејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҢгҖҒдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒЁгғҡгғҶгғӯгҒ®е№»гҒӢгӮүиӘӯгҒҝеҸ–гӮӢз•°йӮҰдәәе®Јж•ҷгҒёгҒ®и»ўжҸӣгҖҒеҫӢжі•гҒЁзҰҸйҹігҖҒиҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдё–з•Ңе®Јж•ҷгҒ®жӢЎејөгӮ’ж·ұгҒҸз…§гӮүгҒ—еҮәгҒҷгҖӮ
дҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒҜгҖҒж•ҷдјҡгҒҢиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎеҶ…йғЁгҒ®иЁҖиӘһгӮ„иҰҸзҜ„гҒ«й–үгҒҳгҒ“гӮӮгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒҚгҖҒиҒ–йңҠгҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒқгҒ®еўғз•ҢгӮ’гҒ“гҒҳй–ӢгҒ‘гҖҒжҠјгҒ—еәғгҒ’гҒҰгҒ„гҒӢгӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгӮ’зӨәгҒҷгҖҒе®Јж•ҷгҒ®ж–Үжі•гҒҢжңҖгӮӮй®®жҳҺгҒ«зҸҫгӮҢгӮӢжң¬ж–ҮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮпјҲOlivet UniversityиЁӯз«Ӣпјүзү§её«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®з« гӮ’еҚҳгҒӘгӮӢжӯҙеҸІзҡ„йҖёи©ұгҒЁгҒ—гҒҰгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢзҰҸйҹігҒҢиҮӘгӮүгӮ’жӢЎејөгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸд»•ж–№гҖҚгӮ’йңІгӮҸгҒ«гҒҷгӮӢе•“зӨәзҡ„е ҙйқўгҒЁгҒ—гҒҰиӘӯгҒҝз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮеҪјгҒҢдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—жҸЎгӮҠгҒ—гӮҒгӮӢзҗҶз”ұгҒҜгҖҒгғҰгғҖгғӨдәәдёӯеҝғгҒ®дҝЎд»°гҒҢз•°йӮҰдәәе®Јж•ҷгҒёгҒЁз§»иЎҢгҒҷгӮӢжұәе®ҡзҡ„и»ўжҸӣгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§иө·гҒ“гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮЁгғ«гӮөгғ¬гғ гҒЁгҒ„гҒҶдҝЎд»°гҒ®дёӯеҝғгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹзҰҸйҹіе®Јж•ҷгҒҢгҖҒгӮөгғһгғӘгӮўгӮ’йҖҡгӮҠгҖҒең°гҒ®жһңгҒҰгҒёгҒЁйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҸгҒқгҒ®йҒҺзЁӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘдәӢ件гҒҜгҖҢең°гҒ®жһңгҒҰгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢгӮӮгҒҜгӮ„жҠҪиұЎзҡ„зҗҶеҝөгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҸҫе®ҹгҒ®жӯҙеҸІгҒ®ж•·еұ…гӮ’и¶ҠгҒҲгӮӢиЎҢзӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮзҹҘгӮүгӮҢгӮӢеҪјгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жң¬ж–ҮгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҖҒж•ҷдјҡгҒҢгҒ©гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гӮӮз№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶйҒёж°‘ж„ҸиӯҳгҒ®иӘҳжғ‘гҒЁжҺ’д»–зҡ„敬иҷ”гҒ®зҝ’ж…ЈгӮ’гҖҒиҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгҒ®гӮӮгҒЁгҒ§зӮ№жӨңгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҒЁеј·иӘҝгҒҷгӮӢгҖӮ
жң¬ж–ҮгҒ®йҮҚгҒҝгҒҜгҖҒдәҢдәәгҒ®дәәзү©гҒ®еҜҫжҜ”гҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢгҖӮгғӯгғјгғһи»ҚгҒ®зҷҫдәәйҡҠй•·гӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒҜгҖҒеёқеӣҪгҒ®з§©еәҸгҒЁеҠӣгӮ’иұЎеҫҙгҒҷгӮӢдәәзү©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒҜеҪјгӮ’гҖҢзҘһгӮ’жҒҗгӮҢгӮӢиҖ…гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰжҸҸгҒҸгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гҖҢз•ҸгӮҢгҖҚгӮ’дҝЎд»°гҒ®еҲқеҝғгҒ§гҒӮгӮҠеҝғиҮ“йғЁгҒ гҒЁи§ЈйҮҲгҒҷгӮӢгҖӮзҘһгӮ’жҒҗгӮҢгӮӢгҒЁгҒҜгҖҒдёҚе®үгӮ„жҒҗжҖ–гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҘһгӮ’и»ҪгӮ“гҒҳгҒӘгҒ„еҶ…зҡ„е§ҝеӢўгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎдәәз”ҹе…ЁдҪ“гӮ’зҘһгҒ®еҫЎеүҚгҒ«зҪ®гҒҸеҺізІӣгҒӘе°ҠеҙҮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®ж•¬иҷ”гҒҜгҖҒдёҖеӣһгҒҚгӮҠгҒ®ж„ҹжғ…гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҝ’ж…ЈеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹзҘҲгӮҠгҒЁж–ҪгҒ—гҒ®гғӘгӮәгғ гҒЁгҒ—гҒҰзҸҫгӮҢгӮӢгҖӮеҪјгҒ®зҘҲгӮҠгҒҜз§Ғзҡ„ж¬ІжңӣгҒ®еҲ—жҢҷгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҘһгҒ®еҫЎеүҚгҒ«иҰҡгҒҲгӮүгӮҢгӮӢзҘҲгӮҠгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҪјгҒ®ж–ҪгҒ—гҒҜиҮӘе·ұиӘҮзӨәгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸйҡЈдәәгӮ’з”ҹгҒӢгҒҷжҒөгҒҝгҒ®йҖҡи·ҜгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒҢзҘһж®ҝгҒ®еҶ…еҒҙгҒёе…ҘгӮҢгҒӘгҒ„з•°йӮҰдәәгҒЁгҒ„гҒҶзӨҫдјҡзҡ„гғ»е®—ж•ҷзҡ„з«Ӣе ҙгҒ«гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚеҫӢжі•гҒҢеҝ—еҗ‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹж ёеҝғгӮ’з”ҹжҙ»гҒЁгҒ—гҒҰе®ҹи·өгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁиЁҖгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҫӢжі•гҒҢеҚҳгҒ«еўғз•Ңз·ҡгӮ’еј•гҒҸйҒ“е…·гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиҒ–гҒ•гҒЁж„ӣгҒёгҒЁдәәй–“гӮ’жӢӣгҒҸйҸЎгҒ гҒЁгҒ„гҒҶеҪјгҒ®дё»ејөгҒЁйҹҝгҒҚеҗҲгҒҶгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ®з·Ҡејөж„ҹгҒҜгҖҒгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®ж•¬иҷ”гҒ гҒ‘гҒ§дҪңгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгӮҲгӮҠжұәе®ҡзҡ„гҒӘгҒ®гҒҜгҖҒгғҡгғҶгғӯгҒ®е№»гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҡгғҶгғӯгҒҜзҘҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҖҒеӨ©гҒӢгӮүеӨ§гҒҚгҒӘеёғгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҷЁгҒҢйҷҚгӮҠгҒҰжқҘгӮӢгҒ®гӮ’иҰӢгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ«жұҡгӮҢгҒҹзҚЈгҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гӮ’иҰӢгҒҰгҖҒгҖҢгҒ»гҒөгҒЈгҒҰйЈҹгҒ№гҒӘгҒ•гҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе‘Ҫд»ӨгӮ’иҒһгҒҸгҖӮгғҰгғҖгғӨгҒ®дјқзөұгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжұҡгӮҢгҒҹйЈҹзү©гҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢзҢ®з«ӢгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮўгӮӨгғҮгғігғҶгӮЈгғҶгӮЈгҒ®жЁҷиӯҳгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе…ұеҗҢдҪ“гҒ®еўғз•ҢгӮ’е®ҲгӮӢиұЎеҫҙгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгғҡгғҶгғӯгҒ®жӢ’еҗҰгҒҜеҫӢжі•гҒёгҒ®еҝ иӘ гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«д»–иҖ…гҒёгҒ®и·қйӣўеҸ–гӮҠгҒЁгҒ„гҒҶе®—ж•ҷзҡ„зҝ’ж…ЈгӮ’йңІе‘ҲгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒЁгҒҚиӘһгӮүгӮҢгҒҹиЁҖи‘үгҒҢгҖҒгҖҢзҘһгҒҢгҒҚгӮҲгӮҒгҒҹзү©гӮ’гҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢгҒҚгӮҲгҒҸгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒ“гҒ®е®ЈиЁҖгӮ’гҖҒе®Јж•ҷгҒ®зҘһеӯҰзҡ„ж–Үз« гҒЁгҒ—гҒҰиӘӯгӮҖгҖӮзҰҸйҹігҒҜгҖҒдәәй–“гҒҢдҪңгӮҠдёҠгҒ’гҒҹзҙ”жҪ”пјҸжұҡгӮҢгҒ®еҲҶйЎһиЎЁгӮ’жү“гҒЎз •гҒҚгҖҒзҘһгҒҢе®ЈиЁҖгҒ•гӮҢгӮӢж–°гҒ—гҒ„еүөйҖ гҒ®з§©еәҸгӮ’й–ӢгҒҸгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®е№»гҒҢдёүеәҰз№°гӮҠиҝ”гҒ•гӮҢгӮӢдәӢе®ҹгҒҜгҖҒиҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгҒҢгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®й ‘гҒӘгҒ•гҒЁжҒҗгӮҢгҒҢеҙ©гӮҢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҫгҒ§еҗҢгҒҳзңҹзҗҶгӮ’еҸҚеҫ©гҒ—гҖҒеҝғгҒ®ж·ұеұӨгҒёгҒЁжҹ“гҒҝиҫјгҒҫгҒӣгҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§ејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒеҫӢжі•гҒЁзҰҸйҹігҒ®й–ўдҝӮгӮ’жң¬ж–ҮгҒ®дёӯеҝғгҒёгҒЁеј•гҒҚеҜ„гҒӣгӮӢгҖӮеҫӢжі•гҒҜдәәгӮ’зҪӘгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«й–үгҒҳиҫјгӮҒгҒҰиҮӘе·ұзҫ©гӮ’жүӢж”ҫгҒ•гҒӣгҖҒзҰҸйҹігҒҜгҒқгҒ®жүӢж”ҫгҒ—гҒ®дёҠгҒ«жҒөгҒҝгӮ’жү“гҒЎз«ӢгҒҰгӮӢгҖӮгғӯгғјгғһжӣё2з« гғ»3з« гҒ§гғ‘гӮҰгғӯгҒҢжҠ•гҒ’гҒӢгҒ‘гҒҹе•ҸгҒ„гҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҢз•°йӮҰдәәгҒҜеҫӢжі•гӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°ж•‘гӮҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҜгҖҒдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе®ҹйҡӣгҒ®еҮәжқҘдәӢгҒЁгҒ—гҒҰи§ЈгҒҚгҒ»гҒҗгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒҜеүІзӨји«–дәүгҒ®дёӯеҝғгҒ®еӨ–еҒҙгҒ«гҒ„гҒҹгҒҢгҖҒзҘһгӮ’жҒҗгӮҢгҖҒзҫ©гӮ’иЎҢгҒҶгҒқгҒ®з”ҹжҙ»гҒҢгҖҢиҰҡгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҖҚгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒ“гӮҢгӮ’гҖҢеҝғгҒ®еүІзӨјгҒ®гҒ—гӮӢгҒ—гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰиӘ¬жҳҺгҒ—гҖҒеҫӢжі•гҒҢеҲ¶еәҰзҡ„гҒ—гӮӢгҒ—гҒ§еҢәеҲҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеҶ…гҒЁеӨ–гҒ®дё–з•ҢгҒҢгҖҒзҰҸйҹігҒ®дёӯгҒ§еҶҚй…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁиЁҖгҒҶгҖӮгӮ¬гғ©гғҶгғӨжӣёгҒ®е®ЈиЁҖвҖ•вҖ•гӮӯгғӘгӮ№гғҲгғ»гӮӨгӮЁгӮ№гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҒҜеүІзӨјгӮӮз„ЎеүІзӨјгӮӮдҪ•гҒ®еҠӣгӮӮгҒӘгҒ„вҖ•вҖ•гҒҜгҖҒ無秩еәҸгҒ®иЁұеҸҜгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж•‘гҒ„гҒ®еҹәжә–гҒҢдәәй–“гҒ®жЁҷиӯҳгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮӯгғӘгӮ№гғҲгҒ®еҚҒеӯ—жһ¶гҒЁеҫ©жҙ»гҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷ秩еәҸгҒ®еӣһеҫ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҖҒејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҢеҫӢжі•гҒ®дҫЎеҖӨгӮ’е»ғжЈ„гҒҷгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮеҪјгҒҜгғӯгғјгғһжӣё3з« 31зҜҖгҒ®и«–зҗҶгҒ«еҫ“гҒ„гҖҒдҝЎд»°гҒҢеҫӢжі•гӮ’з„ЎгҒ«гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚеҫӢжі•гӮ’зўәз«ӢгҒҷгӮӢгҒЁеј·иӘҝгҒҷгӮӢгҖӮеҫӢжі•гҒ®ж ёеҝғгҒҜгҖҒиҒ–гҒ•гҒЁж„ӣгҖҒзҘһгҒ®еҫЎеүҚгҒ§гҒ®з•ҸгӮҢгҒЁйҡЈдәәгҒёгҒ®иІ¬д»»гҒЁгҒ„гҒҶеҖ«зҗҶзҡ„е®ҹдҪ“гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзҰҸйҹігҒҜгҒқгҒ®е®ҹдҪ“гӮ’ж–°гҒ—гҒ„еҘ‘зҙ„гҒ®еҠӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮйЈҹзү©иҰҸе®ҡгӮ„зҘӯгӮҠгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе„ҖзӨјзҡ„иЈ…зҪ®гҒҜжҷӮд»Јзҡ„еҪ№еүІгӮ’зөӮгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒиҒ–гҒ•гҒёгҒ®еҝ—еҗ‘гҒҜж¶ҲгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒ“гҒ®зӮ№гҒ§гҖҒзҸҫд»Јж•ҷдјҡгҒҢйҷҘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„дәҢгҒӨгҒ®жҘөз«ҜвҖ•вҖ•еҫӢжі•дё»зҫ©зҡ„жҺ’д»–жҖ§гҒЁгҖҒеўғз•ҢгҒӘгҒҚж”ҫд»»вҖ•вҖ•гӮ’еҗҢжҷӮгҒ«иӯҰжҲ’гҒҷгӮӢгҖӮзҰҸйҹігҒҜеўғз•ҢгӮ’ж¶ҲгҒ—еҺ»гӮӢгҒҢгҖҒиҒ–гҒ•гӮ’ж¶ҲгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮжҒөгҒҝгҒҜиҰҸзҜ„з ҙеЈҠгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҝғгҒ®ж–°гҒ—гҒ•гҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгӮӢеҖ«зҗҶзҡ„еүөйҖ гҒ гҖҒгҒЁеҪјгҒҜиЁҖгҒҶгҖӮ
дҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒҢзӨәгҒҷж–°гҒ—гҒ•гҒҜгҖҒжҖқжғігҒ®и»ўжҸӣгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®еҮәдјҡгҒ„гҒЁйЈҹеҚ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе…·зҸҫеҢ–гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгғҡгғҶгғӯгҒҜгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®дҪҝиҖ…гҒҹгҒЎгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҖҒгӮ«гӮӨгӮөгғӘгӮўгҒёдёӢгӮҠгҖҒз•°йӮҰдәәгҒ®е®¶гҒ«е…ҘгӮӢгҖӮгғҰгғҖгғӨдәәгҒЁз•°йӮҰдәәгҒ®еўғз•ҢгҒҢжңҖгӮӮз·»еҜҶгҒ«еғҚгҒҸй ҳеҹҹгҒҢгҖҢе…ұгҒ«йЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒ гҒЈгҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®е ҙйқўгҒҜзҘһеӯҰи«–дәүд»ҘдёҠгҒ®иЎқж’ғгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒгғҡгғҶгғӯгҒҢгҖҢз§ҒгӮӮдәәй–“гҒ§гҒҷгҖҚгҒЁиЁҖгҒҶе§ҝеӢўгҒ«жіЁзӣ®гҒҷгӮӢгҖӮе®Јж•ҷгҒҜдёҠгҒӢгӮүдёӢгҒёгҒ®ж–ҪгҒ—гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҗҢгҒҳдәәй–“гҒЁгҒ—гҒҰд»–иҖ…гӮ’е°ҠйҮҚгҒҷгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢгҖӮзҰҸйҹіе®Јж•ҷгҒҢиӘ¬еҫ—еҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒ®гҒҜгҖҒи«–зҗҶгҒ®зІҫе·§гҒ•гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзҰҸйҹігҒҢдәәгӮ’дәәгҒЁгҒ—гҒҰжүұгҒҶгҒқгҒ®д»•ж–№гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиҮӘгӮүгҒ®зңҹе®ҹжҖ§гӮ’зӨәгҒҷгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҶгҒҲгҒ«еҪјгҒҜгҖҒе®Јж•ҷгӮ’еҚҳгҒӘгӮӢеЎҖгҒ®и§ЈдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгӮҲгӮҠгҖҒй–ўдҝӮгҒ®еҶҚж§ӢжҲҗгҒЁгҒ—гҒҰиӘӯгӮҖгҒ№гҒҚгҒ гҒЁиЁҖгҒҶгҖӮеЎҖгҒҜеҙ©гӮҢгҒҰзөӮгӮҸгӮҠгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҙ©гӮҢгҒҹе ҙжүҖгҒ«ж–°гҒ—гҒ„йЈҹеҚ“гҒЁж–°гҒ—гҒ„е…ұеҗҢдҪ“гҒҢе»әгҒҰдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§иҒ–йңҠдҪ“йЁ“гҒҢзҸҫгӮҢгӮӢгҖӮгғҡгғҶгғӯгҒҢгӮӨгӮЁгӮ№гғ»гӮӯгғӘгӮ№гғҲгҒ®жӯ»гҒЁеҫ©жҙ»гҖҒзҪӘгҒ®иөҰгҒ—гҒ®жҒөгҒҝгӮ’е®ЈиЁҖгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжңҖдёӯгҒ«гҖҒиҒ–йңҠгҒҢз•°йӮҰдәәгҒҹгҒЎгҒ®дёҠгҒ«дёӢгӮӢгҖӮз•°иЁҖгӮ’иӘһгӮҠзҘһгӮ’гҒ»гӮҒгҒҹгҒҹгҒҲгӮӢзҸҫиұЎгҒҜиЎЁйқўзҡ„гҒ«гҒҜи¶…иҮӘ然зҡ„дәӢ件гҒ гҒҢгҖҒејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒқгҒ®жң¬иіӘгӮ’гҖҒж•‘гҒ„гҒ®жҷ®йҒҚжҖ§гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзҘһгҒ®иӘҚиЁјгҒЁгҒ—гҒҰи§ЈйҮҲгҒҷгӮӢгҖӮиҒ–йңҠгҒҜж•ҷдјҡгҒ®й–Җз•ӘгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҘһгҒ®е®Јж•ҷгӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢдё»дҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдәәй–“гҒҢиЁӯгҒ‘гҒҹиіҮж јеҜ©жҹ»гӮ’и¶ҠгҒҲгӮӢд»•ж–№гҒ§иҮЁгҒҫгӮҢгӮӢгҖӮеүІзӨјгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹдҝЎиҖ…гҒҹгҒЎгҒҢй©ҡгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒиҒ–йңҠгҒ®еғҚгҒҚгҒҢиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®еӣІгҒ„гҒ®еҶ…еҒҙгҒ«й–үгҒҳиҫјгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒз„Ўж„ҸиӯҳгҒ«д»®е®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ®иЎқж’ғгҒҜгҖҢз•°йӮҰдәәгӮӮиҒ–йңҠгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжғ…е ұгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҘһгҒҢгҒҷгҒ§гҒ«еҪјгӮүгӮ’гҒҚгӮҲгӮҒгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе®ЈиЁҖгҒҢгҖҒзҸҫе®ҹгҒ®дёӯгҒ§зўәиӘҚгҒ•гӮҢгӮӢеҮәжқҘдәӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүгғҡгғҶгғӯгҒҜгҖҢгҒ гӮҢгҒҢж°ҙгҒ§гғҗгғ—гғҶгӮ№гғһгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жӯўгӮҒгӮүгӮҢгӮҲгҒҶгҒӢгҖҚгҒЁиЁҖгҒҶгҖӮдәәй–“гҒ«гҒҜжӯўгӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶе‘ҠзҷҪгҒҜгҖҒе®Јж•ҷгҒ®дё»е°ҺжЁ©гҒҢж•ҷдјҡгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸзҘһгҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢи¬ҷйҒңгҒ®иЁҖи‘үгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
ејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҢгҒ“гҒ®жң¬ж–ҮгӮ’д»Ҡж—ҘгҒ®ж•ҷдјҡгҒ«йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒеҪјгҒҜиҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгӮ’жҠҪиұЎзҡ„ж„ҹеӢ•гӮ„еҖӢдәәзҡ„дҪ“йЁ“гҒёгҒЁйӮ„е…ғгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮгӮҖгҒ—гӮҚиҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгҒЁгҒҜгҖҒж•ҷдјҡгӮ’гӮҲгӮҠеәғгҒ„дё–з•ҢгҒёжҠјгҒ—еҮәгҒҷеҠӣгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиҰӢзҹҘгӮүгҒ¬д»–иҖ…гҒёиҝ‘гҒҘгҒҸгҒҹгӮҒгҒ«з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еҒҸиҰӢгӮ’и§ЈдҪ“гҒҷгӮӢиғҪеҠӣгҒ гҒЁиЁҖгҒҶгҖӮгҒ гҒӢгӮүеҪјгҒҜгҖҒгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®зҘҲгӮҠгҒЁж–ҪгҒ—гҒҢзҘһгҒ®иЁҳжҶ¶гҒ«иҰҡгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒе®Јж•ҷгҒ®еҮәзҷәзӮ№гҒҜе·ЁеӨ§гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж—ҘеёёгҒ®ж•¬иҷ”гҒЁйҡЈдәәж„ӣгҒ гҒЁеј·иӘҝгҒҷгӮӢгҖӮзҘҲгӮҠгҒҜеӨ©гӮ’й–ӢгҒҸйҚөгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж–ҪгҒ—гҒҜең°гҒ®з—ӣгҒҝгҒ«и§ҰгӮҢгӮӢжүӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзҘҲгӮҠгҒ гҒ‘гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰж–ҪгҒ—гҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°дҝЎд»°гҒҜиҮӘе·ұжІЎе…ҘгҒ®зҘһз§ҳдё»зҫ©гҒёеӮҫгҒҚгҖҒж–ҪгҒ—гҒ гҒ‘гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰзҘҲгӮҠгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°дҝЎд»°гҒҜи¶…и¶ҠгӮ’еӨұгҒЈгҒҹеҚҡж„ӣгҒёгҒЁе№іжқҝеҢ–гҒҷгӮӢгҖӮгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒҢжҸЎгҒЈгҒҹдәҢгҒӨгҒ®и»ёгҒҜгҖҒж•ҷдјҡгҒҢгҒ©гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гӮӮеӨұгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гғҗгғ©гғігӮ№ж„ҹиҰҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒҫгҒҹејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒгғҡгғҶгғӯгҒЁгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒҢеҮәдјҡгҒҶжҷӮй–“гҒ®дәӨе·®гӮ’гҖҢзҘһгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰи§ЈйҮҲгҒҷгӮӢгҖӮдәәй–“гҒ®дјҒз”»гҒҜдәәгӮ’йӣҶгӮҒгӮӢгҒҢгҖҒиҒ–йңҠгҒҜдәәгӮ’зөҗгҒіеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҖӮгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒҢеҚҲеҫҢдёүжҷӮгҒ”гӮҚе№»гӮ’иҰӢгҖҒгғҡгғҶгғӯгҒҢжӯЈеҚҲгҒ”гӮҚзҘҲгҒЈгҒҰе№»гӮ’иҰӢгҒҹеҫҢгҖҒгҒқгҒ®дәҢгҒӨгҒ®еҮәжқҘдәӢгҒҢзІҫеҜҶгҒ«еҷӣгҒҝеҗҲгҒЈгҒҰдёҖгҒӨгҒ®еҮәдјҡгҒ„гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж‘ӮзҗҶзҡ„йҖЈзөҗгҒҜгҖҒе®Јж•ҷгҒҢжҲҰз•ҘгҒ®з”Јзү©гҒ§гҒӮгӮӢд»ҘеүҚгҒ«гҖҒгҒҷгҒ§гҒ«еӮҷгҒҲгӮүгӮҢгҒҹйӯӮгҒёеҗ‘гҒ‘гҒҰзҘһгҒҢйҒ“гӮ’й–ӢгҒӢгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдҝЎй јгӮ’иҰҒжұӮгҒҷгӮӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®дҝЎй јгҒҢи–„гӮҢгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒж•ҷдјҡгҒҢж•°еӯ—гҒЁжҲҗжһңгҒ«еҹ·зқҖгҒ—гҖҒд»–иҖ…гӮ’еҜҫиұЎеҢ–гҒҷгӮӢиӘӨгӮҠгҒ«йҷҘгӮҠгҒҶгӮӢгҒЁиӯҰжҲ’гҒҷгӮӢгҖӮеҸҚеҜҫгҒ«иҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгӮ’дҝЎй јгҒҷгӮӢж•ҷдјҡгҒҜгҖҒзӣёжүӢгӮ’зөұиЁҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸдёҖгҒӨгҒ®йӯӮгҒЁгҒ—гҒҰиҰӢгҒӨгӮҒгҖҒеҮәдјҡгҒ„гӮ’ж”Ҝй…ҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸд»•гҒҲгӮӢй–ўдҝӮгҒёгҒЁеӨүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ
дҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ®еҪұйҹҝгҒҜгҖҒгҒқгҒ®з« гҒ®дёӯгҒ§зөӮгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҖӮжӯҙеҸІзҡ„еҮәжқҘдәӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гӮЁгғ«гӮөгғ¬гғ дјҡиӯ°гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®и»ўжҸӣгҒ®е…ұеҗҢдҪ“зҡ„зөҗе®ҹгҒЁгҒ—гҒҰгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°иЁҖеҸҠгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«зҙҖе…ғ49пҪһ50е№ҙгҒ”гӮҚгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒқгҒ®дјҡиӯ°гҒ§гҖҒеҲқд»Јж•ҷдјҡгҒҜз•°йӮҰдәәдҝЎиҖ…гҒ«еүІзӨјгӮ’еј·еҲ¶гҒҷгӮӢгҒ№гҒҚгҒӢгӮ’жүұгҒ„гҖҒзөҗеұҖгҖҒеҝ…й ҲжқЎд»¶гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еүІзӨјгӮ’иҰҒжұӮгҒ—гҒӘгҒ„ж–№еҗ‘гҒ§ж•ҙзҗҶгҒ—гҒҹгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒ“гҒ®дәӢе®ҹгӮ’гҖҒгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘдәӢ件гҒҢеҖӢдәәгҒ®ж„ҹеӢ•гҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒж•ҷдјҡгҒ®е…¬зҡ„иӯҳеҲҘгҒёгҒЁгҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҹжөҒгӮҢгҒ®дёӯгҒ§зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶеҠ©гҒ‘гӮӢгҖӮиҒ–йңҠгҒ®еғҚгҒҚгҒҜгҖҒгҒ„гҒӨгӮӮе…ұеҗҢдҪ“зҡ„иӯҳеҲҘгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰжӯҙеҸІгҒ®дёӯгҒ«ж №гӮ’дёӢгӮҚгҒҷгҖӮе№»гҒЁз•°иЁҖгҒҢеҖӢдәәгӮ’иҲҲеҘ®гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§жӯўгҒҫгӮүгҒҡгҖҒж•ҷдјҡгҒ®ж§ӢйҖ гҒЁж–ҮеҢ–гҖҒдјқзөұгҒЁиҰҸзҜ„гӮ’еҲ·ж–°гҒҷгӮӢж–№еҗ‘гҒёжөҒгӮҢгҒҰгҒ„гҒҸгҒЁгҒҚгҖҒиҒ–йңҠдҪ“йЁ“гҒҜеҲқгӮҒгҒҰе®Јж•ҷгҒ®зҸҫе®ҹгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®ең°зӮ№гҒ§ејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒгҖҢдё–з•Ңе®Јж•ҷгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’еҚҳгҒӘгӮӢең°зҗҶзҡ„жӢЎејөгҒЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮдё–з•ҢеҢ–гӮ’зөҢйЁ“гҒҷгӮӢ21дё–зҙҖгҒ®ж•ҷдјҡгҒҜгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®еёқеӣҪдё»зҫ©зҡ„е®Јж•ҷгҒ®еҪұгӮ’зңҒеҜҹгҒ—гҖҒж–°гҒ—гҒ„е®Јж•ҷгғ‘гғ©гғҖгӮӨгғ гӮ’жЁЎзҙўгҒҷгҒ№гҒҚгҒ гҒЁиЁҖгҒҶгҖӮгӮӮгҒ—гҖҢе®Јж•ҷең°гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢд»–иҖ…гӮ’еҜҫиұЎеҢ–гҒҷгӮӢеҚұйҷәгӮ’гҒҜгӮүгӮҖгҒӘгӮүгҖҒж•ҷдјҡгҒҜзҘһгҒ®е®Јж•ҷвҖ•вҖ•Missio DeiвҖ•вҖ•гҒ®иҰ–зӮ№гҒёжҲ»гӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮзҘһгҒҢе…ҲгҒ«иЎҢгҒӢгӮҢгҖҒж•ҷдјҡгҒҜгҒқгҒ®и¶іи·ЎгҒ«еҗҢиЎҢгҒҷгӮӢеҚ”еғҚиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒ“гҒ®иҰ–зӮ№гӮ’дҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒЁзөҗгҒігҒӨгҒ‘гҖҒж•ҷдјҡгҒҢиҮӘеҲҶгҒ®е®үе…Ёең°еёҜгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮӢзһ¬й–“гҖҒе®Јж•ҷгҒҜж•ҷеӢўжӢЎеӨ§гҒёжӯӘгҒҝгҖҒзҰҸйҹігҒҜж–ҮеҢ–зҡ„е„Әи¶Ҡж„ҹгҒ®йҒ“е…·гҒёи»ўиҗҪгҒ—гҒҶгӮӢгҒЁиЁәж–ӯгҒҷгӮӢгҖӮеҸҚеҜҫгҒ«гҖҒгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®е®¶гҒёе…ҘгҒЈгҒҹгғҡгғҶгғӯгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж•ҷдјҡгҒҢд»–иҖ…гҒ®ж•·еұ…гӮ’и¶ҠгҒҲгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒзҰҸйҹігҒҜеҶҚгҒіжң¬жқҘгҒ®ијқгҒҚгӮ’еӣһеҫ©гҒҷгӮӢгҖӮ
еҗҢжҷӮгҒ«еҪјгҒҜгҖҒзҰҸйҹігҒ®ж ёеҝғгӮ’жӣҮгӮүгҒӣгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁз№°гӮҠиҝ”гҒ—еј·иӘҝгҒҷгӮӢгҖӮж–ҮеҢ–зҡ„йҒ©еҝңгҒҢзҰҸйҹігҒ®зӣёеҜҫеҢ–гҒёеӨүиіӘгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒе®Јж•ҷгҒҜгӮўгӮӨгғҮгғігғҶгӮЈгғҶгӮЈгӮ’еӨұгҒҶгҖӮдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ§гғҡгғҶгғӯгҒ®иӘ¬ж•ҷгҒҜжҳҺзўәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮӨгӮЁгӮ№гғ»гӮӯгғӘгӮ№гғҲгҒ®еҚҒеӯ—жһ¶гҖҒеҫ©жҙ»гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒқгҒ®еҗҚгӮ’дҝЎгҒҳгӮӢиҖ…гҒ«дёҺгҒҲгӮүгӮҢгӮӢзҪӘгҒ®иөҰгҒ—гҒ®жҒөгҒҝгҒҢдёӯеҝғгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж ёеҝғгҒҢжҸәгӮүгҒҗгҒЁгҒҚгҖҒж•ҷдјҡгҒҜеЎҖгӮ’и¶ҠгҒҲгӮӢд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҖҒеЎҖгҒ®еӨ–гҒ®иЁҖиӘһгӮ’еҖҹгӮҠгҒҰиҮӘеҲҶгҒ®гғЎгғғгӮ»гғјгӮёгӮ’з©әгҒ«гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶйҒҺгҒЎгӮ’зҠҜгҒ—гҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҒЁжҢҮж‘ҳгҒҷгӮӢгҖӮгӮҶгҒҲгҒ«еҪјгҒҜгҖҒжң¬иіӘгҒҜе …гҒҸжҸЎгӮҠгҖҒж–№жі•гҒҜи¬ҷйҒңгҒ«ж–°гҒ—гҒҸгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҒЁгҒ„гҒҶе®Јж•ҷеҺҹеүҮгӮ’еј·иӘҝгҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеҫӢжі•гҒЁзҰҸйҹігҒ®й–ўдҝӮгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢйҡӣгӮӮеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжң¬иіӘгҒҜзҘһгҒҢжҲҗгҒ—йҒӮгҒ’гӮүгӮҢгӮӢж•‘гҒ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж–№жі•гҒҜиҒ–йңҠгҒҢжҷӮд»ЈгҒЁж–ҮеҢ–гҒ®дёӯгҒ§й–ӢгҒӢгӮҢгӮӢйҒ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
д»Ҡж—ҘгҒ®дё–з•ҢгҒҜгҖҒзү©зҗҶзҡ„еӣҪеўғгӮҲгӮҠгӮӮзЎ¬гҒ„еҝғзҗҶзҡ„еӣҪеўғгӮ’дҪңгӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдәәзЁ®гҒЁж–ҮеҢ–гҖҒзөҢжёҲеҠӣгҒЁеӯҰжӯҙгҖҒдё–д»ЈгҒЁжҖ§гҖҒзҗҶеҝөгҒЁе—ңеҘҪгҒҢдәәгӮ’еҲҶгҒ‘гҖҒгҒқгҒ®еҲҶиЈӮгҒҜе®—ж•ҷе…ұеҗҢдҪ“гҒ®еҶ…еҒҙгҒ«гӮӮжҹ“гҒҝиҫјгӮҖгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒҢиӘһгӮӢгҖҢз•°йӮҰдәәгҖҚгҒҢеҚҳгҒ«еҸӨд»ЈгҒ®йқһгғҰгғҖгғӨдәәгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒд»Ҡж—ҘгҒ®ж•ҷдјҡгҒҢгҖҢйҰҙжҹ“гӮҒгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒӮгӮүгӮҶгӮӢд»–иҖ…гҒ®еҗҚгҒ«гҒӘгӮҠгҒҶгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жғіиө·гҒ•гҒӣгӮӢгҖӮз•°йӮҰдәәгҒЁгҒҜз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еӨ–гҒ«гҒ„гӮӢиӘ°гҒӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®ж…ЈгӮҢиҰӘгҒ—гӮ“гҒ иҰҸзҜ„гҒ§е®ҡзҫ©гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„дәәгҖ…гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢеҝғең°гӮҲгҒ„иЁҖиӘһгҒ§жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„дё–з•ҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж•ҷдјҡгҒҢеҪјгӮүгӮ’гҖҢжұҡгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶зһ¬й–“гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜзҘһгҒ®гҒҚгӮҲгӮҒгӮ’еҗҰе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүеҪјгҒҜгҖҒж•ҷдјҡгҒҢиҮӘгӮүгҒ®еЎҖгӮ’зӮ№жӨңгҒҷгӮӢйңҠзҡ„зңҒеҜҹгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҖӮз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢзҜүгҒ„гҒҹеЎҖгҒҜгҖҒж•ҷзҗҶгӮ’е®ҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚзӣ®гҒ§гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜдјқзөұгӮ’е®ҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҫҺеҗҚгҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜжҒҗгӮҢгҒЁе„Әи¶Ҡж„ҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеј·еҢ–гҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮиҒ–йңҠгҒҜгҒқгҒ®еЎҖгӮ’еҙ©гҒҷгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҒЁгҒҚгҒ«з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®дҝЎд»°зҡ„еёёиӯҳгӮ’жҸәгҒ•гҒ¶гӮӢд»•ж–№гҒ§иӘһгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®з®ҮжүҖгҒ§ејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒе®Јж•ҷгҒ®зҸҫе®ҹгӮ’йЈҹеҚ“е…ұеҗҢдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰе…·дҪ“еҢ–гҒҷгӮӢгҖӮгҒ гӮҢгҒҢж•ҷдјҡгҒ®дёӯгҒ§йЈҹеҚ“гҒ«зқҖгҒ‘гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒ гӮҢгҒҢе…ұеҗҢдҪ“гҒ®ж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒ«еҸӮдёҺгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒ гӮҢгҒҢзү©иӘһгҒ®дёӯеҝғгҒ«з«ӢгҒӨгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸгҒ„гҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢйҒӢе–¶е•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸзҰҸйҹігҒ®ж”ҝжІ»еӯҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғҡгғҶгғӯгҒҢгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®е®¶гҒ«ж»һеңЁгҒ—дәӨгӮҸгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶиЁҳйҢІгҒҜгҖҒе®Јж•ҷгҒҢдёҖеӣһйҷҗгӮҠгҒ®иЁӘе•ҸгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе…ұгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢжҷӮй–“гҒ®е…ұжңүгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒзҸҫд»Јж•ҷдјҡгҒҢзҹӯжңҹиЎҢдәӢгӮ„гӮӨгғҷгғігғҲдёӯеҝғгҒ®дјқйҒ“гӮ’и¶…гҒҲгҖҒй–ўдҝӮзҡ„гӮұгӮўгҒЁжҢҒз¶ҡзҡ„ејҹеӯҗиЁ“з·ҙгҒ®йҒ“гҒёйҖІгӮҖгӮҲгҒҶдҝғгҒҷгҖӮдёҖгҒӨгҒ®йӯӮгӮ’ж•°еӯ—гҒ§ж•°гҒҲгҒҹзһ¬й–“гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгӮ’зҷҫдәәйҡҠй•·гҒЁгҒ„гҒҶжЁҷиӯҳгҒ гҒ‘гҒ§иҰӢгӮӢиӘӨгӮҠгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒҜдёҖ家еәӯгҒ®й•·гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҸӢдәәгӮ„иҰӘж—ҸгӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒҝгҒ“гҒЁгҒ°гӮ’иҒһгҒ“гҒҶгҒЁгҒ—гҒҹзңҹеүЈгҒӘжұӮйҒ“иҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®жұӮйҒ“иҖ…гҒ®еҝғиҮ“гҒ«еұҠгҒҸиЁҖиӘһгҒҜгҖҒзөұиЁҲгҒ®иЁҖиӘһгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸдәәж јзҡ„еҮәдјҡгҒ„гҒ®иЁҖиӘһгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
зҘҲгӮҠгҒҢзҘһгҒ®еүҚгҒ«иҰҡгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁж–ҪгҒ—гҒҢе…ұгҒ«жӯ©гӮҖгҒЁгҒҚгҖҒе®Јж•ҷгҒҜеӨ©гҒЁең°гӮ’еҗҢжҷӮгҒ«жҠұгҒҸгҖӮгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒҢзӨәгҒ—гҒҹ敬иҷ”гҒЁж–ҪгҒ—гҒ®зөҗеҗҲгҒҜгҖҒзҰҸйҹігҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢе ҙжүҖгӮ’гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒй–ӢгҒҸйңҠзҡ„еңҹеЈҢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҶгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒҷгӮӢгҖӮдё–з•ҢгҒҜж•ҷдјҡгҒ®иЁҖи‘үгӮҲгӮҠе…ҲгҒ«гҖҒж•ҷдјҡгҒ®ж…ӢеәҰгӮ’иӘӯгӮҖгҖӮж•ҷдјҡгҒҢиӢҰгҒ—гӮҖйҡЈдәәгӮ’иҰӢжҚЁгҒҰгҒӘгҒҢгӮүзҰҸйҹігӮ’иӘһгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ®иЁҖи‘үгҒҜз©әиҷҡгҒӘгҒ“гҒ гҒҫгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮеҸҚеҜҫгҒ«ж•ҷдјҡгҒҢж„ӣгҒ®е®ҹи·өгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдҝЎй јгҒ®з©әй–“гӮ’дҪңгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒзҰҸйҹігҒҜз„ЎзҗҶгҒ«жҠјгҒ—иҫјгӮҖи«–зҗҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиҮӘ然гҒ«жҹ“гҒҝиҫјгӮҖе…үгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®е…үгӮ’гҖҢжҒөгҒҝгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒ§жҚүгҒҲгӮӢгҖӮжҒөгҒҝгҒҜе®үгҒЈгҒҪгҒ„еҜӣе®№гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҚҒеӯ—жһ¶гҒ®д»ЈдҫЎгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹзҘһгҒ®ж–°гҒ—гҒ„зҸҫе®ҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®зҸҫе®ҹгҒҜж„ӣгҒЁиҒ–гҒ•гӮ’еҗҢжҷӮгҒ«иҰҒжұӮгҒҷгӮӢгҖӮ
иҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгҒҜгҒҫгҒҹгҖҒж•ҷдјҡгҒҢеӨұж•—гӮ’жҒҗгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮгғҡгғҶгғӯгҒ«гӮӮжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮз•°йӮҰдәәгҒ®е®¶гҒ«е…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе®—ж•ҷзҡ„йқһйӣЈгӮ’еј•гҒҚеҸ—гҒ‘гӮӢйҒёжҠһгҒ гҒЈгҒҹгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ11з« гҒ§еҪјгҒҜгӮЁгғ«гӮөгғ¬гғ ж•ҷдјҡгҒӢгӮүе•ҸгҒ„гҒҹгҒ гҒ•гӮҢжү№еҲӨгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гғҡгғҶгғӯгҒҜиҮӘеҲҶгҒ®йҒёжҠһгӮ’еҖӢдәәзҡ„еҶ’йҷәгҒЁгҒ—гҒҰејҒиӯ·гҒӣгҒҡгҖҒзҘһгҒҢгҒӘгҒ•гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иЁјиЁҖгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§е…ұеҗҢдҪ“гҒ®зҗҶи§ЈгӮ’еҫ—гӮӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒе®Јж•ҷгҒҢе…ұеҗҢдҪ“зҡ„иІ¬д»»гҒЁзөҗгҒігҒӨгҒҸгҒ№гҒҚгҒ гҒЁиЁҖгҒҶгҖӮгҖҢиҒ–йңҠгҒҢгҒқгҒҶгҒ•гҒӣгҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢиІ¬д»»еӣһйҒҝгҒ®гӮ№гғӯгғјгӮ¬гғігҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе…ұеҗҢдҪ“гӮ’иӘ¬еҫ—гҒ—гҖҒе…ұгҒ«иӯҳеҲҘгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶе°ҺгҒҸи¬ҷйҒңгҒӘиЁјиЁҖгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚиҒ–йңҠдҪ“йЁ“гҒҜеҲҶиЈӮгҒ®зЁ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдёҖиҮҙгҒ®еңҹеҸ°гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ
ејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҢеј·иӘҝгҒҷгӮӢгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®дё»йЎҢгҒҜгҖҒзҰҸйҹігҒ®иЁҖиӘһгҒҢжҢҒгҒӨжҷ®йҒҚжҖ§гҒЁзҝ»иЁігҒ®иӘІйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғҡгғҶгғӯгҒ®иӘ¬ж•ҷгҒҜгғҰгғҖгғӨзҡ„иғҢжҷҜгӮ’жҢҒгҒӨиЁҖиӘһгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢгҒҢгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«гҖҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәәгҒ«зҰҸйҹігҒҢй–ӢгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе®ЈиЁҖгҒёйҖІгӮҖгҖӮеҪјгҒҜгӮӨгӮЁгӮ№гғ»гӮӯгғӘгӮ№гғҲгӮ’дёҮзү©гҒ®дё»гҒЁгҒ—гҒҰе®ЈгҒ№дјқгҒҲгҖҒгҒқгҒ®ж–№гҒҢгғҰгғҖгғӨдәәгҒ®гғЎгӮ·гӮўгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰе…Ёдё–з•ҢгҒ®дё»жЁ©иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒд»Ҡж—ҘгҒ®ж•ҷдјҡгӮӮеҗҢгҒҳзҝ»иЁіиӘІйЎҢгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҶгҖӮзҰҸйҹігҒҜеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒ®зҰҸйҹігӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢиЁҖиӘһгҒҜж–ҮеҢ–гҒЁдё–д»ЈгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮӢгҖӮгӮҶгҒҲгҒ«дё–з•Ңе®Јж•ҷгҒҜиЁҖиӘһеӯҰзҡ„гғ»ж–ҮеҢ–дәәйЎһеӯҰзҡ„ж„ҹиҰҡгӮ’иҰҒжұӮгҒ—гҖҒд»–иҖ…гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’е°ҠйҮҚгҒҷгӮӢеӯҰгҒігҒ®е§ҝеӢўгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгғҡгғҶгғӯгҒҢгҒҫгҒҡгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®е®¶гӮ’иЁӘгҒӯгҖҒеҪјгҒ®и©ұгӮ’иҒһгҒҚгҖҒеҪјгҒ®з”ҹжҙ»гҒ®ж–Үи„ҲгҒ®дёӯгҒ§зҰҸйҹігӮ’иӘһгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒд»Ҡж—ҘгҒ®ж•ҷдјҡгӮӮгҖҢе…ҲгҒ«иҒһгҒҚгҖҒе…ҲгҒ«еӯҰгҒ¶гҖҚи¬ҷйҒңгӮ’еӣһеҫ©гҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®еҺҹзҗҶгҒҜгғҮгӮёгӮҝгғ«жҷӮд»ЈгҒ®е®Јж•ҷгҒ«гӮӮгҒқгҒ®гҒҫгҒҫйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгӮӘгғігғ©гӮӨгғіз©әй–“гҒҜеӣҪеўғгӮ’дҪҺгҒҸгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гӮўгғ«гӮҙгғӘгӮәгғ гҒЁгҒ„гҒҶж–°гҒ—гҒ„еЎҖгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢгҖӮж•ҷдјҡгҒҢгғЎгғҮгӮЈгӮўе®Јж•ҷгӮ’еұ•й–ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ§гҒ•гҒҲгҖҒжӢЎж•ЈгӮ„еҶҚз”ҹж•°гӮ’жҲҗеҠҹгҒ гҒЁиӘӨи§ЈгҒӣгҒҡгҖҒй–ўдҝӮгҒ®ж·ұгҒ•гҒЁзңҹе®ҹжҖ§гӮ’жҢҮжЁҷгҒЁгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒҢзӨәгҒ—гҒҹе®Јж•ҷгҒҜгғҗгӮӨгғ©гғ«гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸиЁӘе•ҸгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮ№гӮӯгғЈгғігҒ§гҒҜгҒӘгҒҸж»һеңЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҠҖиЎ“гҒЁгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’йҒ“е…·гҒЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гҒӨгҒӨгӮӮгҖҒзөҗеұҖе®Јж•ҷгҒ®жң¬иіӘгҒҜдәәгҒЁдәәгҒ®й–“гҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгӮӢдҝЎй јгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒқгҒ®дҝЎй јгҒ®дёҠгҒ§е®ЈиЁҖгҒ•гӮҢгӮӢгӮӨгӮЁгӮ№гғ»гӮӯгғӘгӮ№гғҲгҒ®зҰҸйҹігҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еҝҳгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҖҒж•ҷдјҡгҒҜж–°гҒ—гҒ„еӘ’дҪ“гҒ®дёӯгҒ§гӮӮеҸӨгҒ„зҰҸйҹігҒ®йҮҚгҒҝгӮ’е®ҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮиҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгҒҜж•ҷдјҡгӮ’гӮҲгӮҠйҖҹгҒҸгҒҷгӮӢгӮҲгӮҠгҖҒгӮҲгӮҠзңҹе®ҹгҒ«гҒ—гҖҒгӮҲгӮҠеәғгҒҸжӢЎж•ЈгҒ•гҒӣгӮӢгӮҲгӮҠгҖҒгӮҲгӮҠж·ұгҒҸж №гҒҘгҒӢгҒӣгӮӢгҖӮ
дҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гӮ’иӘӯгӮҖгҒЁгҒҚиҰӢиҗҪгҒЁгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®иҰҒзҙ гҒҜгҖҒзҘһгҒҢдёҖдәәгҒ®дәәзү©гҒ гҒ‘гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰеғҚгҒӢгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®е№»гҖҒгғҡгғҶгғӯгҒ®е№»гҖҒгҒқгҒ—гҒҰдәҢдәәгҒ®й–“гӮ’иЎҢгҒҚжқҘгҒҷгӮӢдҪҝиҖ…гҒҹгҒЎгҒ®еҫ“й ҶгҒҢдёҖгҒӨгҒ®зү©иӘһгӮ’еҪўдҪңгӮӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒ“гҒ®зӮ№гӮ’жҢҷгҒ’гҖҒе®Јж•ҷгҒҜгӮ«гғӘгӮ№гғһзҡ„жҢҮе°ҺиҖ…дёҖдәәгҒ®ж„Ҹеҝ—гҒ§йҖІгӮҖгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе№іеҮЎгҒӘеҫ“й ҶгҒҢйҖЈгҒӘгҒЈгҒҰе®ҢжҲҗгҒҷгӮӢе…ұеҗҢдҪңжҘӯгҒ гҒЁиЁҖгҒҶгҖӮгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒҢйғЁдёӢгӮ’йҒЈгӮҸгҒҷеҫ“й ҶгҖҒгғҡгғҶгғӯгҒҢз–‘гҒ„гӮ’дёӢгӮҚгҒ—гҒҰеҗҢиЎҢгҒҷгӮӢеҫ“й ҶгҖҒгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®е®¶ж—ҸгҒЁеҸӢдәәгҒҢгҒҝгҒ“гҒЁгҒ°гӮ’еҫ…гҒӨеҫ“й ҶгҖҒгҒқгҒ—гҒҰиҒ–йңҠгҒҢиҮЁгҒҫгӮҢгӮӢгҒЁгҒҚзҘһгӮ’гҒӮгҒҢгӮҒгӮӢиіӣзҫҺгҒ®еҫ“й ҶгҒҢгҖҒдёҖгҒӨгҒ®жөҒгӮҢгҒЁгҒ—гҒҰгҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒЁгҒҚж•ҷдјҡгҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒҢдё»дәәе…¬гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸзҘһгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢеҷЁе…·гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еӯҰгҒ¶гҖӮеҷЁе…·гҒҜиҮӘеҲҶгӮ’иӘҮзӨәгҒӣгҒҡгҖҒзӣ®зҡ„гӮ’зӨәгҒҷгҖӮе®Јж•ҷгӮӮеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж•ҷдјҡгҒҢиҮӘеҲҶгҒ®еҗҚгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚе®Јж•ҷгҒҜжӯӘгҒҝгҖҒгӮӨгӮЁгӮ№гҒ®еҗҚгҒҢй«ҳгҒҸдёҠгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒҚе®Јж•ҷгҒҜгҒҚгӮҲгҒҸдҝқгҒҹгӮҢгӮӢгҖӮ
ејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒ“гҒ®гҖҢгҒҚгӮҲгҒ•гҖҚгӮ’еҖӢдәәгҒ®йңҠжҖ§гҒ®дёӯгҒ«гӮӮиҰӢгҒ„гҒ гҒҷгҖӮеҪјгҒҜгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®ж•¬иҷ”гӮ’дҝЎд»°гҒ®дҪ“иіӘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘ¬жҳҺгҒ—гҖҒдҪ“иіӘгҒҜдёҖжңқдёҖеӨ•гҒ«еӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гӮҶгҒҲгҖҒжҜҺж—ҘгҒ®зҘҲгӮҠгҒЁе°ҸгҒ•гҒӘж–ҪгҒ—гҒҢз©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгӮүгӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒҶгҖӮдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ®еҠҮзҡ„гҒӘиҒ–йңҠдҪ“йЁ“гҒҜгҖҒгҒӮгӮӢж—ҘзӘҒ然иҗҪгҒЎгҒҹзЁІеҰ»гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®е®¶гҒ«й•·гҒҸз©ҚгӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹз•ҸгӮҢгҒ®з©әж°—гҒ®дёӯгҒ§иө·гҒ“гҒЈгҒҹеҮәжқҘдәӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҗҢж§ҳгҒ«гғҡгғҶгғӯгҒ®е№»гӮӮгҖҒеҪјгҒ®зҘҲгӮҠгҒ®жңҖдёӯгҒ«дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҒ“гҒ®дәӢе®ҹгӮ’гҖҒе®Јж•ҷгҒҢеӨ–гҒёеҗ‘гҒӢгҒҶжҙ»еӢ•гҒ§гҒӮгӮӢд»ҘеүҚгҒ«гҖҒеҶ…гҒёеҗ‘гҒӢгҒҶ敬иҷ”гҒ®иЁ“з·ҙгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷиЁјжӢ гҒЁгҒ—гҒҰи§ЈйҮҲгҒҷгӮӢгҖӮж•ҷдјҡгҒҢзҘҲгӮҠгӮ’еӨұгҒҲгҒ°иӯҳеҲҘгӮ’еӨұгҒ„гҖҒиӯҳеҲҘгӮ’еӨұгҒҲгҒ°е®Јж•ҷгҒҜжөҒиЎҢгҒ«жөҒгҒ•гӮҢгҖҒжөҒиЎҢгҒ«жөҒгҒ•гӮҢгӮҢгҒ°зҰҸйҹігҒ®дёӯеҝғгӮ’иҰӢеӨұгҒҶгҖӮгӮҶгҒҲгҒ«еҪјгҒҜгҖҒж•ҷдјҡгҒҢзҘҲгӮҠгҒЁгҒҝгҒ“гҒЁгҒ°гҖҒгҒқгҒ—гҒҰйҡЈдәәж„ӣгҒ®е®ҹи·өгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒиҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгҒ«ж•Ҹж„ҹгҒӘе…ұеҗҢдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰиЁ“з·ҙгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҒЁдҝғгҒҷгҖӮ
зөҗеұҖгҖҒдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒЁејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒ®и§ЈйҮҲгҒҢз§ҒгҒҹгҒЎгҒ«жҠ•гҒ’гҒӢгҒ‘гӮӢе•ҸгҒ„гҒҜеҚҳзҙ”гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҒ гӮҢгӮ’гҖҢжұҡгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖӮз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҒ©гӮ“гҒӘеЎҖгӮ’дҝЎд»°гҒ®еҗҚгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«зҜүгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖӮз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®зҘҲгӮҠгӮ’иҒһгҒӢгӮҢгӮӢзҘһгӮ’дҝЎгҒҳгҒӘгҒҢгӮүгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҡЈдәәгҒ«дјҡгҒҶгҒ“гҒЁгӮ’жҒҗгӮҢгҒҰгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгҖӮдё–з•Ңе®Јж•ҷгӮ’иӘһгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒе°ҸгҒ•гҒӘйЈҹеҚ“гҒ§д»–иҖ…гӮ’жӯ“еҫ…гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҜеҗқе—ҮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®е•ҸгҒ„гҒёгҒ®зӯ”гҒҲгӮ’и«–дәүгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸеҫ“й ҶгҒ®дёӯгҒ«иҰӢгҒ„гҒ гҒҷгҖӮгҖҢгӮҸгҒҹгҒ—гҒҢгҒҚгӮҲгӮҒгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҒгҒҚгӮҲгҒҸгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҜгҖҒзҘһеӯҰзҡ„ж–Үз« гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«еҖ«зҗҶзҡ„е‘Ҫд»ӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж•ҷдјҡи«–зҡ„еҺҹеүҮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®иЁҖи‘үгҒ«еҫ“гҒҶгҒЁгҒҚгҖҒж•ҷдјҡгҒҜгӮҲгӮҠеҢ…ж‘Ӯзҡ„гҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮҲгӮҠиҒ–гҒ„е…ұеҗҢдҪ“гҒёгҒЁиӮІгҒӨгҖӮеҢ…ж‘ӮгҒЁгҒҜеҹәжә–и§ЈдҪ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸжҒөгҒҝгҒ®жӢЎејөгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиҒ–гҒ•гҒЁгҒҜд»–иҖ…жҺ’йҷӨгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸж„ӣгҒ®зҙ”зІӢгҒ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒЁгӮҠгӮҸгҒ‘еӨҡж–ҮеҢ–зӨҫдјҡгҒ®дёӯгҒ«гҒӮгӮӢйҹ“еӣҪж•ҷдјҡгҒҜгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„е®Јж•ҷең°гӮ’йҒ гҒ„еӣҪгҒЁгҒ—гҒҰгҒ гҒ‘иҰҸе®ҡгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒ®дҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гғЎгғғгӮ»гғјгӮёгӮ’д»Ҡж—ҘгҒ®зҸҫе®ҹгҒ«з…§гӮүгҒ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒӘгӮүгҖҒйҹ“еӣҪгҒ®и·Ҝең°гӮ„гӮӯгғЈгғігғ‘гӮ№гҖҒиҒ·е ҙгӮ„гӮӘгғігғ©гӮӨгғігғ»гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒҢгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«гӮөгғһгғӘгӮўгҒ§гҒӮгӮҠгӮ«гӮӨгӮөгғӘгӮўгҒЁгҒӘгӮҠгҒҶгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҘгҒӢгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§ж•ҷдјҡгҒҢзӨәгҒ—гҒҶгӮӢжңҖгӮӮиӘ¬еҫ—еҠӣгҒӮгӮӢзҰҸйҹігҒҜгҖҒеҫӢжі•гҒ®зү©е·®гҒ—гҒ§дәәгӮ’еҲҶйЎһгҒҷгӮӢж…ӢеәҰгӮ’дёӢгӮҚгҒ—гҖҒзҰҸйҹігҒ®жҒөгҒҝгҒ§дәәгӮ’иҰӢзӣҙгҒҷиҰ–з·ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®иҰ–з·ҡгҒҢж №гҒҘгҒҸгҒЁгҒҚгҖҒзҘҲгӮҠгҒҜиҮӘе·ұдёӯеҝғзҡ„иҰҒжұӮгҒӢгӮүйӣўгӮҢгҒҰйҡЈдәәгӮ’жҠұгҒҸеҹ·гӮҠжҲҗгҒ—гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒж–ҪгҒ—гҒҜж–ҪдёҺгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸйҖЈеёҜгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒз•°йӮҰдәәе®Јж•ҷгҒҜиҰӢзҹҘгӮүгҒ¬д»–иҖ…гҒёиҝ‘гҒҘгҒҸзҫ©еӢҷгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҘһгҒ®еҝғгҒ«еҸӮдёҺгҒҷгӮӢе–ңгҒігҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®жөҒгӮҢгҒ®дёӯгҒ§гҖҒејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҢдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« иӘ¬ж•ҷгӮ’зөҗгҒ¶гҒЁгҒҚж®ӢгҒҷзөҗи«–гҒҜгҖҒе®Јж•ҷгҒ®жӢЎејөгҒ“гҒқгҒҢиҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгҒёгҒ®еҫ“й ҶгҒ гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјгҒҜж•ҷдјҡгҒ«гҖҒеҶ…еҒҙгҒ®е®үе…ЁгҒӘеўғз•ҢгҒ«е®үдҪҸгҒӣгҒҡгҖҒзҘһгҒ®еүҚгҒ«иҰҡгҒҲгӮүгӮҢгӮӢзҘҲгӮҠгҒЁж–ҪгҒ—гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ—гҖҒеҒҸиҰӢгӮ’з •гҒӢгӮҢгӮӢиҒ–йңҠгҒ®еЈ°гҒ«еҝңзӯ”гҒӣгӮҲгҒЁдҝғгҒҷгҖӮж•ҷдјҡгҒҜиҮӘе·ұдҝқеӯҳгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮж•ҷдјҡгҒҜгӮӨгӮЁгӮ№гғ»гӮӯгғӘгӮ№гғҲгӮ’иЁјгҒ—гҒҷгӮӢиҒ–йңҠгҒ®е…ұеҗҢдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰеҸ¬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒЁгғҡгғҶгғӯгҒ®еҮәдјҡгҒ„гҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҸ¬гҒ—гҒҢгҒ„гҒӢгҒ«е…·дҪ“зҡ„гҒ§гҖҒгҒ„гҒӢгҒ«зҸҫе®ҹзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒқгҒ®еҮәдјҡгҒ„гҒҢеҸҜиғҪгҒ гҒЈгҒҹзҗҶз”ұгҒҜгҖҒдёҖдәәгҒҢеҒүеӨ§гҒӘжұәж–ӯгӮ’гҒ—гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҘһгҒҢгҒҷгҒ§гҒ«жӯҙеҸІгҒ®дёӯгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгҒҹйҒ“гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®йҒ“гҒ®дёҠгҒ«зҘҲгӮӢдәәгҒЁеҫ“гҒҶдәәгҒҢгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®жӢЎејөгҒЁгҒҜгҖҒзҰҸйҹігӮ’йҖҡгҒ—гҒҰзҘһгҒҢдәәгҒ®еҝғгҒ«жҲҗгҒ—йҒӮгҒ’гӮүгӮҢгӮӢзөұжІ»гҒ®жӢЎејөгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҶгҒҲгҒ«д»Ҡж—ҘгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гӮ’ж”№гӮҒгҒҰиӘӯгӮҖгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®дәӢ件гӮ’еӣһжғігҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢд»ҠгҒ“гҒ“гҖҚгҒ§еҶҚгҒігӮігғ«гғҚгғӘгӮӘгҒ«еҮәдјҡгҒ„гҖҒеҶҚгҒігғҡгғҶгғӯгҒ®е№»гӮ’зөҢйЁ“гҒӣгӮҲгҒЁгҒ„гҒҶеҸ¬гҒ—гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜз•°йӮҰдәәгӮ’йҒ гҒ„д»–ж–ҮеҢ–еңҸгҒ®дәәгҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒ гҒ‘иҖғгҒҲгҒҢгҒЎгҒ гҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®гҒқгҒ°гҒ«гҒ„гӮӢз•°йӮҰдәәвҖ•вҖ•з§»дҪҸеҠҙеғҚиҖ…гҖҒйӣЈж°‘гҖҒжңӘдҝЎиҖ…гҒ®е®¶ж—ҸгҖҒж•ҷдјҡгҒ®еӨ–гҒ«гҒ„гӮӢиӢҘиҖ…гҖҒеӮ·гҒӨгҒ„гҒҹдҝЎд»°иҖ…вҖ•вҖ•гҒҢгҒ„гӮӢгҖӮеҪјгӮүгҒ«зҰҸйҹігӮ’дјқгҒҲгӮӢгҒЁгҒҜгҖҒеҪјгӮүгӮ’гҖҢдҝ®жӯЈгҖҚгҒҷгӮӢдҪңжҘӯгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҘһгҒҢгҒҷгҒ§гҒ«еҪјгӮүгҒ®еҶ…гҒ«еғҚгҒӢгӮҢгҒҹз—•и·ЎгӮ’иҰӢеҲҶгҒ‘е°ҠйҮҚгҒ—гҖҒгӮӨгӮЁгӮ№гғ»гӮӯгғӘгӮ№гғҲгҒ®жҒөгҒҝгӮ’е…ұгҒ«еҲҶгҒӢгҒЎеҗҲгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгҒҜгҖҒж•ҷдјҡгҒ®иЁҖиӘһгӮ’гӮҲгӮҠж”»ж’ғзҡ„гҒ«гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮҲгӮҠжӯ“еҫ…гҒ®иЁҖиӘһгҒёгҒЁеӨүгҒҲгӮӢгҖӮеҫӢжі•гҒҢзҪӘгӮ’жҡҙгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еҒҸиҰӢгӮӮжҡҙгҒӢгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒзҰҸйҹігҒҜгҒқгҒ®еҒҸиҰӢгӮ’ж–ӯзҪӘгҒ§зөӮгӮҸгӮүгҒӣгҒҡгҖҒжӮ”гҒ„ж”№гӮҒгҒ®йҒ“гҒёе°ҺгҒҸгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е®Јж•ҷгҒҢжӢЎејөгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒҜгҖҒж•ҷдјҡгҒҢгӮҲгӮҠеӨҡгҒҸгҒ®дәәгӮ’гҖҢз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еҒҙгҖҚгҒ«еј•гҒҚиҫјгӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮҲгӮҠеӨҡгҒҸгҒ®йҡЈдәәгӮ’зҘһгҒҢж„ӣгҒ•гӮҢгӮӢеӯҳеңЁгҒЁгҒ—гҒҰиӘҚгӮҒгҖҒеҪјгӮүгҒЁе…ұгҒ«гӮӨгӮЁгӮ№гғ»гӮӯгғӘгӮ№гғҲгҒ®зҰҸйҹігҒ®гҒҶгҒЎгҒ«ж–°гҒ—гҒ„е…ұеҗҢдҪ“гӮ’е»әгҒҰдёҠгҒ’гҒҰгҒ„гҒҸйҒҺзЁӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®йҒҺзЁӢгҒ§з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒеҫӢжі•гҒҢжҡҙгҒҸиҮӘе·ұдёӯеҝғжҖ§гҒЁжҺ’д»–жҖ§гӮ’иӘҚгӮҒгҖҒзҰҸйҹігҒҢдёҺгҒҲгӮӢиҮӘз”ұгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдә’гҒ„гӮ’жӯ“еҫ…гҒҷгӮӢиЎ“гӮ’еӯҰгҒ¶гҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®еӯҰгҒігҒ“гҒқгҒҢгҖҒејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҢдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« иӘ¬ж•ҷгҒ§з№°гӮҠиҝ”гҒ—е‘јгҒіиҰҡгҒҫгҒҷж ёеҝғе®ҹи·өгҒёгҒЁгҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҖӮ敬иҷ”гҒЁж–ҪгҒ—гҒҢеҲҶйӣўгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶж—ҘеёёгҒ®гғӘгӮәгғ гӮ’ж•ҙгҒҲгҖҒгҒҝгҒ“гҒЁгҒ°гҒЁзҘҲгӮҠгҒ®дёӯгҒ§иҒ–йңҠгҒ®е°ҺгҒҚгӮ’иӯҳеҲҘгҒ—гҖҒгғҰгғҖгғӨдәәгҒЁз•°йӮҰдәәгӮ’еҲҶгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹеЎҖгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«д»Ҡж—Ҙз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®еҶ…гҒ«ж®ӢгӮӢиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„е·®еҲҘгҒ®еЈҒгҒЁжӯЈзӣҙгҒ«еҗ‘гҒҚеҗҲгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒЁгҒҚж•ҷдјҡгҒҜгҖҒгҖҢжӢЎејөгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’жҲҗй•·гҒ®дҝ®иҫһгҒЁгҒ—гҒҰж¶ҲиІ»гҒӣгҒҡгҖҒжҒөгҒҝгҒҢжӢЎејөгҒ•гӮҢгӮӢж–№еҗ‘гҒЁгҒ—гҒҰзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®йҒҺзЁӢгҒ§з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒиҒ–йңҠдҪ“йЁ“гӮ’ж–°гҒ—гҒҸе®ҡзҫ©гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮз•°иЁҖгӮ„зҘһз§ҳдҪ“йЁ“гҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүиҒ–йңҠгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҘһз§ҳдҪ“йЁ“гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүиҒ–йңҠгҒ«жәҖгҒЎгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгӮӮйҷҗгӮүгҒӘгҒ„гҖӮдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ§гҒ®иҒ–йңҠдҪ“йЁ“гҒҜгҖҒж•ҷдјҡгҒҢгғҗгғ—гғҶгӮ№гғһгӮ’зҰҒгҒҳгӮүгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ»гҒ©жҳҺзўәгҒӘгҒ—гӮӢгҒ—гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«е…ұеҗҢдҪ“гҒҢз•°йӮҰдәәгӮ’е…„ејҹгҒЁгҒ—гҒҰеҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢеҖ«зҗҶзҡ„еҠӣгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮд»Ҡж—ҘгҒ®ж•ҷдјҡгҒҢзөҢйЁ“гҒҷгҒ№гҒҚиҒ–йңҠдҪ“йЁ“гӮӮгҖҒзөҗеұҖгҖҒй–ўдҝӮгҒ®еЎҖгҒҢеҙ©гӮҢгҖҒдә’гҒ„гҒ®йЈҹеҚ“гҒ«еә§гӮҠе…ұгҒ«зҘһгӮ’гҒӮгҒҢгӮҒгҖҒзҰҸйҹіе®Јж•ҷгҒҢз”ҹжҙ»гҒ®иЁҖиӘһгҒ«гҒӘгӮӢеӨүеҢ–гҒЁгҒ—гҒҰзҸҫгӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеүІзӨји«–дәүгҒҢж•ҷдјҡгҒ®жң¬иіӘгӮ’жҸәгҒ•гҒ¶гҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒд»Ҡж—ҘгӮӮж•ҷдјҡгҒҜгҖҢгҒ гӮҢгҒҢз§ҒгҒҹгҒЎгҒЁе…ұгҒ«гҒҷгӮӢиіҮж јгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸгҒ„гҒ§жҸәгҒ•гҒ¶гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—дҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ®зӯ”гҒҲгҒҜз°ЎжҳҺгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзҘһгҒҢгҒҚгӮҲгӮҒгӮүгӮҢгҒҹиҖ…гӮ’гҖҒжұҡгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҒқгҒ®иЁҖи‘үгҒ®еүҚгҒ§гҖҒеҶҚгҒізҘҲгӮҠгҖҒеҶҚгҒіж–ҪгҒ—гҖҒеҶҚгҒіиҰӢзҹҘгӮүгҒ¬йҡЈдәәгҒёеҗ‘гҒ‘гҒҰжӯ©гҒҝеҮәгҒҷгҖӮејөгғҖгғ“гғҮзү§её«гҒҢжҸЎгӮҠгҒ—гӮҒгӮӢдҪҝеҫ’гҒ®еғҚгҒҚ10з« гҒ®зҰҸйҹігҒҜгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰд»Ҡж—ҘгӮӮдё–з•Ңе®Јж•ҷгҒ®йҒ“гӮ’й–ӢгҒ„гҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ
ж—Ҙжң¬гӮӘгғӘгғҷгғғгғҲгӮўгғғгӮ»гғігғ–гғӘгғјж•ҷеӣЈ