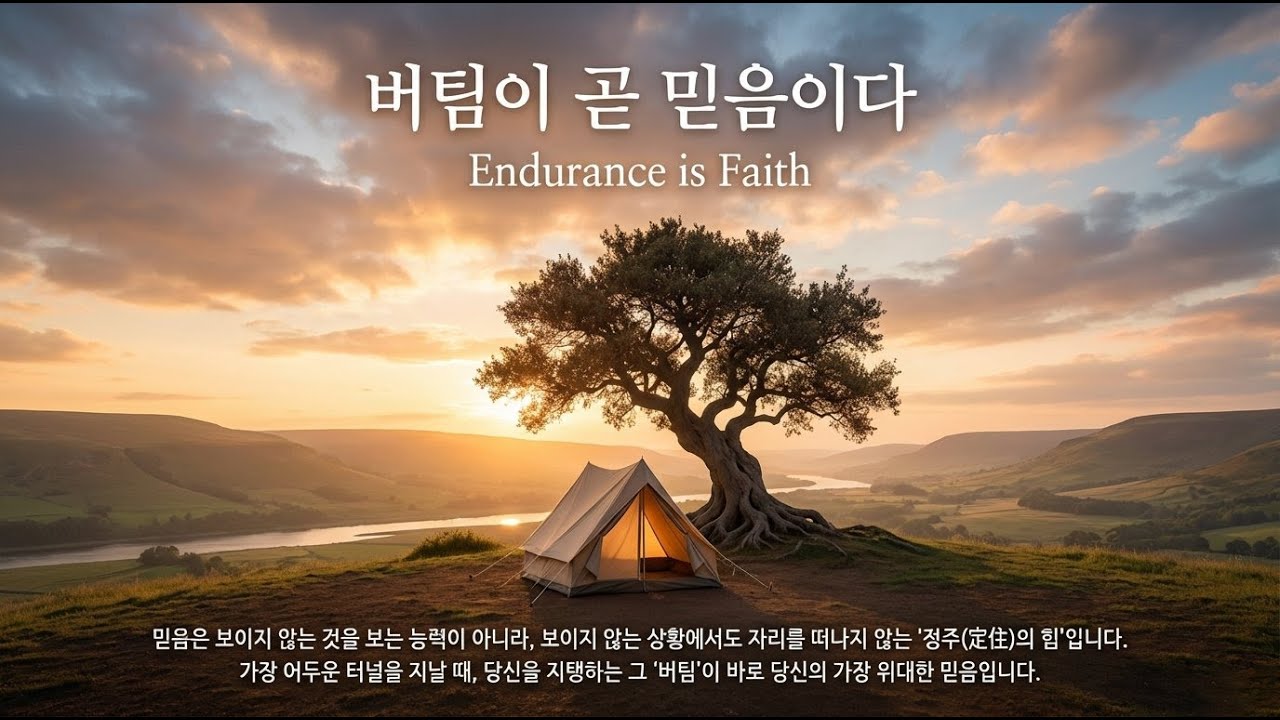張ダビデ牧師が、主の祈りの「今日も私たちに日用の糧をお与えください」を軸に据え、神の国と歴史、物質と霊性、赦しと聖霊、そして所有中心の生から愛中心の生への転換を綿密に解き明かす。日々の経済的必要を超えて、他者を生かす「三つのパン」の霊性を通して、having mode から loving mode へと向かうキリスト者の存在様式を深く省察する神学的・実践的黙想である。
マタイによる福音書6章の主の祈りの中心部に置かれている「今日も私たちに日用の糧をお与えください」という願いは、あまりにも馴染み深いために、つい形式的な文句として流してしまいがちである。しかし張ダビデ牧師の説教の中で、この一節は、キリスト者の存在論的目的、人生の方向性、愛のかたち全体を貫く決定的な鍵として新たに照らし出される。彼は、この祈りが単に「今日食べて生きる分のご飯をください」という素朴な生活の祈りではなく、神の国へと動いていく歴史、私たちの具体的な経済生活、そして他者への愛が交差する地点で捧げられる、深い神学的要請であることを綿密に示していく。そしてそのすべての解釈の結論には、張ダビデ牧師が繰り返し強調する視点の転換、すなわち having mode から loving mode への転換、言い換えれば「何をどれだけ所有するか」ではなく「どのように愛しながら存在するか」が人生の本質であるという福音的宣言が置かれている。
主の祈りは二つの根本的前提を宣言しながら始まる。「御名が聖とされますように」、「御国が来ますように」。オリベット大学の設立者でもある張ダビデ牧師は、この二つの願いを、人間存在の目的を規定する根本命題として解釈する。私はなぜ存在するのか、歴史はどこへ向かって流れているのか――この問いの前で、聖書は明確に答える。神の御名が聖く崇められるように、神の国が来るように、すでに天において完全に成就している神の御心が、この地上においても実現するように生きること、それが人間の創造目的なのだ。ヘブライ人への手紙が「この世はあの世の型と影にすぎない」と証言するように、彼は天の御国を本体、この世をその本体に映し出された影、すなわちプロジェクションとして理解する。ゆえに歴史とは偶然の放浪ではなく、すでに天で決定されている神の国という終末論的結論へと収斂していく巨大な旅路である。このような歴史意識の上に、主の祈りの次の願い「日用の糧をお与えください」が置かれていることは、きわめて意味深い。
興味深いのは、このような荘厳な宇宙的ビジョンが宣言された直後に、すぐさまきわめて現実的な主題――パンとご飯、お金の問題――が登場するという事実である。「日用の糧」は決して抽象的な霊的象徴ではない。英語訳聖書が “daily bread” と訳すように、文字通り毎日食べるパン、日々の食卓、今日必要な生活費を指す。張ダビデ牧師はこの点を「きわめて正直な祈り」であると言う。神が私たちに教えてくださった祈りは、決して「食べて生きる問題は自分たちで何とかしなさい」と非現実的な霊性だけを求めてはいない。むしろ「あなたがたが食べて生きるものを求めよ。今日必要な糧を切実に求めよ」と命じておられる。同時に申命記8章3節は「人はパンだけで生きるのではなく、主の口から出るすべての言葉によって生きる」と釘を刺す。パン、すなわちパンとお金は、生活の必要条件ではあるが、決して十分条件ではない。この緊張――物質の重要性を認めつつも、物質に絶対的価値を与えないという緊張――の上に、聖書的霊性は立っている。人は御言葉によって生きなければならないが、その御言葉は私たちのパンの問題を決して見捨てない。
このとき、主の祈りに登場する一つの独特なギリシア語が、新たな意味を現わす。「日用の」と訳される “epiousios(エピウシオス)” という語は、新約聖書全体の中で主の祈りにしか用いられていない稀少な表現であり、「今日のための、その日にどうしても必要な、存在を維持するのに不可欠な」というニュアンスを併せ持っている。言い換えれば、この祈りは貪欲な蓄積を正当化する嘆願ではなく、「今日一日を信仰をもって生きていくのに十分な分」、神に依り頼んで生きていけるだけのゆとりを求める祈りである。ところが張ダビデ牧師の解釈において、この「十分さ」はあくまで自分個人だけの十分さで終わらない。ここでルカによる福音書11章が、非常に決定的な洞察を与える。
ルカによる福音書11章は、ルカ版の主の祈りと並行して、祈りの核心的テーマを三つに圧縮して提示する。神の国、日用の糧、そして赦し。いちばん前には、歴史の終着点であり目標である神の国が置かれ、最後にはすべての人間関係を再構成する赦しが置かれている。そしてそのあいだ、きわめて現実的など真ん中に「日用の糧」がある。まるで神の国と赦しという二本の巨大な柱のあいだをつなぐ橋のように、この日用の糧の願いが位置している。神の国のために生き、人を赦し、壊れた関係を回復していくそのすべての過程の中には、いつもパンとご飯、お金という具体的な必要が入り込んでくる。神はこの物質的必要そのものを祈りの主題として許しつつ、その必要を通して、愛の生き方と神の国を学ばせてくださる。
ルカは続けて、この日用の糧の重みを説明するために、「真夜中に友人の家を訪ねた人」のたとえを紹介する。ユダヤ社会において真夜中に他人の家の戸を叩くことは、常識と礼儀に深く反する行為であった。戸が閉まれば一日が終わったことを意味し、家族がすでに一つの部屋に横になって眠っている状態で戸を叩くことは、共同体のインナーサークルに踏み込むのと同じことであった。ところが一人の人が、真夜中に友人の家にやって来て、戸をドンドンと叩きながらこう言う。「友よ、パンを三つ貸してくれ。」一つでもなく、二つでもなく、なんと三つである。張ダビデ牧師はこの「三つ」という表現に神学的象徴性を見いだす。一食を満たすだけならパン一つで十分だろう。二つであれば、今食べてもう一度食べるくらいの余裕である。しかし三つは、自分を越えて他者に分け与えることのできる分、すなわち他人のために備えられた予備を意味する。三つを求めるというのは、「自分の空腹を満たすため」だけでなく、「今自分の家を訪ねてきた飢えた客を食べさせるため」に求めることである。この瞬間、「日用の糧」という概念は一気に拡張される。日用の糧とは、「自分一人がかろうじて生き延びる最低限」ではなく、「自分と隣人が共に人間らしく生きることのできるゆとり」である。
ユダヤ人は、「貸しても借りはしない」という旧約の精神を抱く民であり、メンツと礼儀を重んじ、相手を不必要に困らせない文化を持っている。そのユダヤ人が真夜中に戸を叩き、パン三つを求めるというのは、常識を超えた大胆な決断である。ところがイエスは、この「無礼に見えるほどしつこい願い」、すなわち強く求め続ける祈り(shameless persistence)を肯定的に評価される。「友だからといっては起きて与えないかもしれないが、そのしつこい願いのゆえに起き上がり、必要なだけを与えるであろう」と。張ダビデ牧師はこの一節から、「自分自身を越えて他者へと向かっていく愛」という強力な原動力を読み取る。この人を真夜中の通りへ、固く閉ざされた戸口へ、決して引き下がらない強請の場へと押し出しているのは、単なる物質的欠乏ではない。飢えた客を食べさせたいという切迫した愛である。その愛がパンを持っている友の心を動かし、ついには「必要なだけ」、十分に与えさせるのである。
この地点で張ダビデ牧師は、現代文明を支配している having mode を正面から批判する。私たちの日常の言葉には “I have …” があふれている。自分が所有している家、資産、スペック(能力・学歴)、人脈が、そのまま自分のアイデンティティと価値であるかのように思われている時代である。しかしこの所有中心のパラダイムは、構造的に欠乏を前提としている。どれだけ持っても常に足りず、もっと持たなければ不安を抑えられないように感じてしまう。一方、福音は having mode から being mode へ、さらに loving mode への変化を求める。単に「どうすれば人間らしく存在できるか」というレベルを越えて、「どうすれば他者のために自分を喜んで差し出しつつ存在できるか」という次元へと進むべきだと言うのである。張ダビデ牧師が用いる loving mode という表現は、まさにこの点を指し示す。自分の必要だけを満たすレベルの日用の糧から、隣人の必要まで共に担って求める三つのパンへと向かう生き方、すなわち自らの所有を愛の通路として用いる存在のあり方が、loving mode である。この転換が実際に起こる時、私たちはもはや「どれだけ多く蓄えたか」で人生を評価せず、「どれほど深く愛したか」で自分の生涯を読み解くようになる。
ルカ11章は続けて、私たちがあまりにもよく知っている御言葉――「求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見いだす。叩きなさい。そうすれば開かれる」――を記している。張ダビデ牧師はこの一節を、単なる「祈りましょう」というスローガンではなく、先に語られた真夜中の友人のたとえと密接に結びついた約束として読む。祈りの出発点は、「求めるなら応えてくださる人格的な神が実際におられる」という信仰である。もし神がおられないなら、人間の生は結局、悲劇的な虚無へと帰結するしかない。しかし神を知る瞬間、まったく異なる可能性の地平が開かれる。祈りはあいまいな自己暗示ではなく、応えてくださる父なる神のもとへと近づく現実的な行為であり、「求める者はすべて受け、探す者は見いだし、叩く者には開かれる」という約束は、神との関係がいかに信頼しうる土台の上に立っているかを示している。
ルカはさらに、親と子の関係を通してこの真理をいっそう説得力をもって解き明かす。子が魚をくださいと言うのに蛇を与える父はおらず、卵をくださいと言うのにサソリを与える父もいない。悪い人間の父ですら、自分の子どもには良いものを与えることを知っているとすれば、まして天の父はどうであろうか。そしてクライマックスの一文が続く。「まして天の父は、求める者たちに聖霊を与えてくださらないことがあろうか。」張ダビデ牧師はこの御言葉を、祈りの究極的な目標として提示する。私たちが祈りによって受ける数多くの賜物の中で、最も決定的で尊い贈り物は、まさに聖霊である。旧約時代には、何世紀に一人出るかどうかという人物が聖霊の油注ぎを受ければ、民全体がその人に注目した。しかし今や、誰であっても求めるなら聖霊を賜物として受ける時代が開かれたのだ。ローマ8章32節が示すように、神はすでに私たちのために、ご自分の御子さえ惜しまずにお与えになった。御子さえ与えてくださった方が、聖霊とその他すべてを与えないはずがない。
ここで重要な問いが生じる。「日用の糧を求める祈り」と「聖霊の賜物」はどのようにつながるのか。聖霊は単に超自然的な賜物を与える霊ではなく、私たちの欲望の構造そのものを新しく形づくる霊である。having mode の貪欲と自己執着を解体し、loving mode の愛と自己放棄を私たちのうちに刻み込んでくださる方である。聖霊を受けた人は、日用の糧を求める仕方からして変えられる。一人で安楽に生きるための安定装置、自分だけのためのセーフティネットを求めるのではなく、神の国のために、飢えた者を食べさせ、裸の者を着せ、虐げられた者を立ち上がらせるための必要を、大胆に求めるようになる。言い換えれば、聖霊は私たちに「三つのパン」を求める勇気を注いでくださる。自分と他者をともに生かすことのできるゆとりを求め、愛のゆえに真夜中でも喜んで戸を叩くことのできる、聖なるずうずうしさを与えてくださる方こそ、聖霊なのである。
張ダビデ牧師はさらに、イエスとペテロが神殿税を納める場面を象徴的に解釈する。イエスがペテロに「湖に行って釣り針を垂れなさい。最初に上がってくる魚の口を開けると一シケル銀貨が見つかる。それを取って、わたしとあなたの分の神殿税を納めなさい」と言われた出来事は、文字通りに見れば奇跡的な供給の物語である。しかし彼はこの場面を、「一人の人を得て、ともに問題を解決しなさい」という霊的なたとえとしても読む。神の国が拡大すればするほど新しい必要が生まれるが、同時に新しい同労者、新しい資源、新しい関係も与えられる。一つの魂が主のもとに立ち帰るということは、その人一人の救いにとどまらず、神の国のために共に献身する友を得る出来事である。この意味で、日用の糧を求める祈りは、すなわち「人」を求める祈りでもある。金銭と資源だけが満たされるのではなく、ともにパンを裂き、神の国のために生きる友が加えられるのである。
現代の資本主義社会の中で、クリスチャンは絶えず試験台の上に立たされている。もっと所有せよという圧力、より多く持たなければ安全ではないと煽る不安マーケティング、より早く成長しなければならないという成果主義が、教会の中にまで深く染み込んでいる。信仰さえも、「どうすれば神をうまく利用して、自分の生存と成功をもう少し安全に設計できるか」という機能的ツールに堕してしまいやすい。まさにこの地点で、張ダビデ牧師が「having mode から loving mode へ転換せよ」と叫ぶことは、きわめて急進的で挑戦的な宣言となる。日用の糧を求めるにしても、自分のためだけに求めるのではなく、神の国と他者のために求めよ、というのである。服が二着あるなら、一着は自分が着るために、もう一着は誰かに差し出すために存在している。三つのパンは、自分が腹一杯食べるためではなく、真夜中にやって来た飢えた友を食べさせるために備えられる余分なのである。この観点から見ると、豊かさの定義そのものが根本から組み替えられる。多く持っている人が豊かなのではなく、多く分かち合う人こそ、本当に豊かな人である。コリントの信徒への第二の手紙8章9節が語るように、主は本来富んでおられたのに、私たちのために自ら貧しくなられ、それによって私たちを真に富ませてくださった。その方に従う弟子は、必然的に同じ軌道をたどることになる。
このような神学的洞察は、具体的な生活のかたちへと結びつくとき、はじめて力を持つ。「今日も私たちに日用の糧をお与えください」と祈るとき、私たちは次のように告白することができる。「神さま、今日私が生きていくのに必要なものを満たしてくださるだけでなく、誰かを食べさせ、着せ、世話をすることができるだけの余分もお与えください。私の米びつと財布と時間と賜物が、自分だけのための倉庫ではなく、神の国のための通路となりますように。」同時にこう自問すべきである。「神さま、もしかして私は、すでに与えられている日用の糧の中から、本来は誰かに流すようにと託された分を、握りしめてはいないでしょうか。」聖霊がこの問いの前で私たちの良心と考えを照らしてくださるとき、私たちは日常の消費や財政の運用、関係と時間の配分を新たに設計しなおすようになる。この再構成こそ、having mode
から loving mode へと移っていく回心のプロセスなのである。
さらに、日用の糧を求める祈りは、いつも赦しの祈りへとつながっていかなければならない。ルカは、神の国―日用の糧―赦しという構造を通して、真の神の国の生き方が、物質と関係の両方に向き合わない限り、完全には成り立たないことを示している。神の国のために生きようとするなら、必ず関係の回復が必要であり、真の回復は赦しなしには不可能である。赦しとは、いつも損を引き受ける側の選択であり、先に手を差し伸べる愛の決断である。ある意味、赦しは物質を分かち合うこと以上に難しい「日用の糧」かもしれない。ある人に対して日々供給しなければならない忍耐、寛容、再び愛することのできる心の余白があるとしたら、それもまた神に求めるべき重要な必要である。「神さま、今日も私がこの人をもう一度愛することができるだけの、心の糧をお与えください。」このように日用の糧とは、パンとご飯とお金を越えて、愛と赦しと忍耐という目に見えない資源全体を含み込む豊かな概念なのである。
結局、張ダビデ牧師の説教が私たちを招いている世界は、単純でありながら、同時に根本的な変革を要求する世界である。天においてすでに完全に成し遂げられている神の国へと歴史は流れており、私たちはその歴史の流れの中で、その国のためにこの地に派遣された存在である。その過程において、私たちは日々日用の糧を求めなければならない。今日食べるもの、今日用いるお金、今日担わなければならない使命と関係のための必要を求めなければならない。しかしその祈りは、「自分一人が生き残るための祈り」にとどまってはならない。飢えた者と貧しい者、疎外された者と弱い者を食べさせ、着せ、世話をし、神の国を引き寄せる愛の通路となるための嘆願でなければならない。そしてこのすべての祈りの頂点には、そのような愛の生を私たちのうちに可能にしてくださる聖霊を求める祈りが据えられていなければならない。
「今日も私たちに日用の糧をお与えください。」この短い一句の中に、神の国と歴史、経済と霊性、赦しと聖霊、having mode と
loving mode がすべて凝縮されている。今こそ、この祈りを口先で暗唱する段階を越えて、存在全体で生き抜くべき時である。今日、自分の食卓と財布、スケジュールと賜物、そして心の奥の余白を見つめながら、次のように祈ることができるだろう。「神さま、私が求める日用の糧の中に、誰かを生かすための三つのパンが含まれるようにしてください。そしてそのパンを最後まで分かち合うことができるように、聖霊によって私を満たしてください。」この告白こそ、張ダビデ牧師が証しする主の祈りの心臓部であり、日用の糧を求める祈りが内包している福音の深みなのである。
日本オリベットアッセンブリー教団